 『エルニーニョ』 『エルニーニョ』 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 加藤: |
|
去年、『小さいおうち』で直木賞を受賞なさった後の第1作ですね。この作品は受賞後に書き始められたのでしょうか? それとも他の作品と並行してお書きになっていたんですか?
|
|

『エルニーニョ』
講談社:刊
|
| 中島: |
|
受賞よりずっと前から書いていました。『小さいおうち』を書き終わって、ひと月くらいしてから書き始めたんです。書き下ろしは久しぶりだったので、他の仕事は一時お断りして、去年の前半はこちらに専念していました。ちょうど賞の選考やら発表やら授賞式やらというころに、おしまいの方を書いていましたね。
|
| 加藤: |
|
女子大生の瑛(てる)という主人公が、同居しているDV男の金を奪って南の町へと逃げ延び、そこで出会ったニノという男の子と共に逃げ続けるお話です。ロード・ノヴェルとしても面白さがある作品だなと感じました。私が傑作だと思っている『イトウの恋』もそうだったと思いますが、中島さんはロード・ノヴェルはお得意なのではないでしょうか?
|
| 中島: |
|
お得意かどうかは…(笑)。でも、旅の話を書くのは好きみたいですね。他にも『ツアー1989』なんかも旅といえば旅ですし。
|
| 加藤: |
|
フィリピン人とのハーフである「ニノ」が、本来の発音では「ニーニョ」であると分かったとき、タイトルと繋がって合点がいきました。さらに読み進めていくと、「エルニーニョ」には「男の子」という意味の他に「幼子イエス」という意味があると分かりました。このタイトルに込められた意味をお聞かせ願えますか?
|
| 中島: |
|
主人公を、フィリピン人とのハーフと決めてから、フィリピン人の友達にメールで相談したんです。「両親のいない子なんだけど、かわいそうな話にはしたくないから、フィリピン人のお母さんがつけた、この子を守ってくれる名前が欲しいんだけど、どんなのがいいかな?」って。そしたら20個くらい教えてくれたんですね。フィリピン神話の英雄やらテレビドラマのヒーローやら。その中で、「ニノ」は日本人にも馴染みやすいし、それにまさに「男の子」だし、「幼子イエス」は子供の守り神だという説明もあって、物語のテーマにぴったりだと思ってつけました。
|
| 加藤: |
|
なるほど。この作品では瑛とニノの逃避行というメインの物語の合間合間に〈灰色の男たち〉や〈ピーター・パンとウェンディー〉のサブストーリーが挿入されます。これがまた、読んでいて面白かったのですが…。
|
| 中島: |
|
ありがとうございます。本を読むことと旅をすることは、どこか似ていて、旅の面白さには、その土地の物語と出会う楽しさがあると思ったので、2人の旅に、サブストーリーを加えてみたくなったんです。そうすることで、小説に少し奥行きが出ればいいなあと思いながら書きました。
|
| 加藤: |
|
私はこの作品を読んで、「逃げてもいいんだな」と、とても楽になった感じがしました。肩の力が抜けた、というか。「森のくまさん」をついつい口ずさんでしまう自分がいます。
|
| 中島: |
|
「森のくまさん」、変な歌ですからね。いきなり熊が出てきて「お逃げなさい」って言う…。おかしいな~って思ってたんですね。その疑問を解決することから、まずは物語が始まったというか。
|
| 加藤: |
|
去年の角田光代さんの『ツリーハウス』もそうでしたし、来月発売になる桐野夏生さんの『ポリティコン』もそう言えると思うのですが、最近、実力ある女性作家たちが「逃げる」ことを肯定するような作品を書く流れがあるような気がしています。「逃亡のススメ」とでも申しましょうか。これは何か符号のようなものがあると思われますか?
|
| 中島: |
|
あらまあ、それは気づきませんでした。でも、時代が物書きに「書け」と迫るということはあるかもしれないですね。やはり、ちょっといまは、時代じたいに息苦しさがある。経済の落ち込みなどが原因で、先の見えない閉塞感が社会全体を覆っているところがあると思います。そこにはもしかしたら「逃げろ」というメッセージが必要なのかもしれないですね。追い詰められて死んでしまったり、他人を刺したり、いじめたりするくらいなら、逃げてしまったほうがいい。私は単純に、DV男からは逃げ出して欲しいという思いがあって書きました。
|
 |
 「来るべき世界の作家たち」 「来るべき世界の作家たち」 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 加藤: |
|
去年、「文学界」10月号に、中島さんが監修なさった「来るべき世界の作家たち」という特集が掲載されたことを記憶しています。IWPについて簡単にご説明していただけますか?
|
|
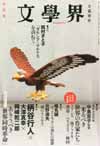
『文学界2010年10月号』
文藝春秋:刊
|
| 中島: |
|
IWPは、インターナショナル・ライティング・プログラムといって、アメリカのアイオワ大学が行っている、作家招聘プログラムです。毎年、秋の2ヶ月半くらいを、アイオワで過ごし、朗読会やパネル・ディスカッションなんかに参加します。私が行った年は、約30ヶ国、36人が参加していました。40年以上も続く、伝統あるもので、過去には中上健次さんとか、島田雅彦さんとか、水村美苗さんなんかが参加して、水村さんは『日本語が亡びるとき』の冒頭に、そこでの経験をお書きになっていますね。
|
| 加藤: |
|
ご参加なさって、率直なご感想は? 中島さんの創作活動に影響はありましたか?
|
| 中島: |
|
すご~く、楽しかったです。(笑)なんだか学生生活をもう1回やったみたいな感じで。世界各国から集まる作家とも、同じ宿舎にいるから、いつのまにか学生寮の仲間みたいになっちゃうんですよ。お互い、すさまじい英語で話してるんですけども。創作活動への影響は、まず、2ヶ月半リラックスしたので、ストレスがなくなって、書きたい気持ちがムクムク湧いて『エルニーニョ』が書けた。(笑)
|
| 加藤: |
|
そうだったんですか!「文学界」に掲載された5作品は中島さんがお選びになったのでしょうか? 5作品についての思いは?
|
| 中島: |
|
中島セレクションです(笑)。どれも思い入れはありますねえ。メールで連絡とって、許可もらって、翻訳の方をお願いしてって、その一連の作業、もちろん、編集の方といっしょにやったんですけども、ドキドキしちゃって。南アフリカの新鋭マクシーン・ケイスの短編を、南アのノーベル賞作家・クッツェーの翻訳者である鴻巣友季子さんにお願いして、OKの返事を頂いたときとか、嬉しかったですしね。あの翻訳特集はおかげさまで好評で、フランスの移民作家マブルーク・ラシュディの『プチ・マリク』と、香港のボルヘスって呼ばれている、董啓章の『地図集』は、単行本化が進みつつあるんです。本が出たら、そのときはよろしくお願いいたします。
|
| 加藤: |
|
しっかりと覚えておきます(笑)!ところで、世界文学の中でご覧になったとき、現在の日本文学の特徴はどういったところにあると思われますか?
|
| 中島: |
|
うーん。私は評論家じゃないから、そういうふうに考えたりしないし、世界×日本っていうふうにも言えないと思うのですが、海外作家は、社会性のあるテーマを選んでいることが多いような気がしました。東欧の作家は、冷戦終了後の混乱を書いているし、フランスの作家は移民の現在を書いている。香港作家は植民地後のアイデンティティを主題にしているし、南アの作家はアパルトヘイト後を書いている。それらが、ジャーナリスティックな書き方ではなく、小説家の視点と筆で書かれていることが印象的でした。ひるがえって日本の小説を見てみると、社会的な要素はあまりダイレクトには描かれなくて、もっと個人の内面に寄り添った方法で現代が描かれている、そんな感じを持ちました。
|
| 加藤: |
|
ありがとうございます。とても勉強になります。
|
 |
 直木賞受賞作『小さいおうち』 直木賞受賞作『小さいおうち』 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 加藤: |
|
ありきたりな質問で恐縮ですが、直木賞を受賞なさって中島さんご自身の中で何か変化はありましたか?
|
|
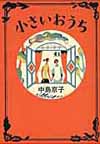
『小さいおうち』
文藝春秋:刊
|
| 中島: |
|
それはね。ものすごく違います。でも、何が違うのかと訊かれると、うまく答えられない(笑)。小学校なんかで、ちょっとお調子者の子を班長さんなんかにして自覚を持たせるようなことがあるでしょう? あれに似てますよ。「おっきな賞もらっちゃったんだしな。ちゃんとしよう」って思う(笑)。以前がちゃんとしてなかったかというと、そんなことはないんですが。
|
| 加藤: |
|
あはは!そうなんですか!『小さいおうち』は本当に素晴らしい作品だと思いました。戦時中、東京郊外の中流家庭に女中として働いていた主人公「タキさん」が、後年、当時の出来事や思い出を回想する、というお話です。この作品の前にも中島さんは『女中譚』という作品を書かれていらっしゃいますね。中島さんにとって「女中」という職業は、書いていて楽しい対象なのではないでしょうか?
|
| 中島: |
|
女中さんというのは、家族の中に深く入り込むけど、家族ではない。ちょっと距離を置いた存在ですね。小説の視点人物として、とても魅力的です。しかも、ある特定の時代にしか、タキさんみたいな女中さんは存在しない。いろいろな意味で、書いてみたいと思っていました。
|
| 加藤: |
|
この作品では、戦時中の庶民の暮らしぶりがとても細かく書かれています。思うように食べ物が手に入らないとき、何で代用するか、とか、どうやって倹約するか、など。
|
| 中島: |
|
当時の女性誌なんかを片っ端から見て、「あら、案外、美味しそう」なんて思ったりしましたよ。自分だったら、こんなふうに工夫するだろうって、創作もまぜたり。いまでも女性誌って、節約ネタが好きでしょ。私も女性誌編集者だったことがあるので、ああいう記事の作り方のノウハウがわかるんです。そんなことを思い浮かべながら、楽しんで書きました。
|
| 加藤: |
|
最後の章で、あっと驚く結末が待っています。この構成の巧みさには唸ってしまいました。
|
| 中島: |
|
小説は、いろんなものを盛り込める、寛容な器だと思うんです。1章から7章までは、あの時代を、女中さんの視点でくっきり立ち上がらせることを主眼に書いたのですが、最終章では、それとはまったく別の要素を盛り込みたいと思いました。小説は、とても自由度の高い散文形式なので、もっといろいろなことができると思うんですよ。現時点での私にはあれがいっぱいいっぱいだけど、楽しんでいただけたなら、とても嬉しいです。
|
 |

