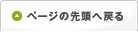※2014/2/28以前の「本の泉」は、5%税込の商品価格を表示しています。 |
| 第112回 2010年12月23日 |
|
幻の名作ついに文庫化!『海炭市叙景』に寄せて | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 いま読むべき紛れもない1冊 本書は、かつて炭鉱の町として栄えていたがすっかり落剥して「もう希望を持つことのできない」町になってしまった地方都市「海炭市」を舞台に、18人の主人公の悲喜こもごもを描いた短篇集です。 (アトレ恵比寿店 加藤泉)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 静かに「生」が光る街 散歩にでて住宅街に迷い込むことがある。そんな時、天災や事故などの世界的なニュースを見た時よりもずっとずっと生々しく「生」を感じてしまう。立ち並ぶ表札の数だけ生活があり、皆が喜びや悲しみを背負って生きている。自分のちっぽけさに思い至る。 (新百合ヶ丘エルミロード店 門脇順子)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 冬の夜に静かに読みたい作品 人々のありふれた暮らしが、風景画のように心に写る、冬の夜に静かに読みたい作品。 (販売促進室 徳永あけみ)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 かじかんだ心を静かに融かしてくれる
(企画開発室 東慶太)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 20年も前に書かれたとは思えない 驚いた。まず、本作がほぼ瀕死(絶版)の状態だったことに。あやうく消えかかった火が本作映画化運動やツイッターから、また再び火を燈したことに。そして読んでまたも驚いた。20年の月日をもろともせず、生きている作品であった。いや、20年も前に書かれたとは思えない、現代を見通しているかのような作品であったこと、強く感銘を与える作品だったことに。 (ルミネ町田店 渋沢良子)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 突出した信念の力 人それぞれの幸せがあって、人それぞれの不幸がある。 (アトレ新浦安店 広沢友樹)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 心に何かが残る。何だろう。 「泣ける!」とか「息をもつかせぬ」という作品ではない。でも、心に何かが残る。何だろう。地方で地味に暮らす登場人物たちは饒舌ではない。世間との関わりや人生の中で胸の奥底にある思いをつぶやく。「で、あなたはこの先何か進路の希望あるの?」。進路指導室で言われた言葉を反すうしながら歩いた昼下がりの住宅街を思い出した。 (出版部 梅田勝)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 何とも言えない愛おしさ かつては炭鉱と漁業で栄えていたがその産業の衰退と共に寂れつつある地方都市「海炭市」に住む人々の様々な人生の断片。十八人の(どちらかと言えばしょぼくれた)主人公による十八篇の(どちらかと言えばしみったれた)エピソードから成る小説で、派手な事件やドラマティックな物語が用意されている訳でもないのに「次はどんな奴らに出逢えるのか、そいつはどんな暮らしをしていてどんな事を考えているのか」というのが気になって頁を繰る手が止まらなくなる。そして一篇一篇読み進めるにつれ自分の胸の内にポッと熱いものが灯り始めるのがわかる。それは、出てくる奴らに対する他人とは思えない共感であり共鳴であり、何とも言えない愛おしさである。一人でも多くの人に彼らと出逢って欲しいと心から願う。 (横浜駅西口店 梅原潤一)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 キラキラと煌いて美しい この本を読んでいて現実をこんなにも生々しく感じるのは、私たちが心の奥底に知らず知らずに抱いている恐れや不安が登場人物たちのそれとシンクロするからだろう。この漠然とした暗いものが文章になりその文章と対峙する時、私はいつも息苦しさを感じる。それでもこの短編たちはキラキラと煌いて美しい。それはちょうど人間の生活が、きれいな部分と暗い部分の二つが渾然一体となりどちらも切り離せないことに似ている。 (アトレ恵比寿店 佐瀬康子)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 誰もが幸せではないけれど まっすぐに生きている バブル経済で日本全体が浮き足立っている中、その恩恵を受けるどころか貧しくなっていく街の人々。この架空の街「海炭市」を舞台に第1章・2章に分かれ、18編のドラマが繰り広げられています。「貧しさ」「仕事」「大切なもの」がキーワードになり登場人物がそれぞれの思いを伝えています。炭鉱夫だった男が炭鉱の閉鎖により職を失い絶望する衝撃の1編から両親の離婚により別荘に1人で過ごしている大学生まで、誰もが幸せではないけれどまっすぐに生きているところが魅力的です。 (書籍外商部 荻野聡子)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 町のリアルを 人間の生を描く 観光地には「絶景」スポットがあって、たくさんの観光客がその美しさに感激の声をあげます。高いところから、または、広いところからのその眺めはいわば「引き」の映像です。この小説はそれとは正反対に「寄り」の映像で描きます。徹底して寄ることで、町のリアルを、人間の生を描くことに成功しています。綺麗な夜景のその1つ1つの灯りには、人間1人1人の営みがあり、命がある。そんなことを改めて考えた1冊でした。 (販売促進室 磯野真一郎)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
 せつなくてやるせない、だけどあたたかい。 18の短編の群像劇の主人公たちは、皆必死にもがいて、悩み苦しみながら生きています。とてもせつなくてやるせない物語ですが、それ以上にあたたかさや温もりを感じるのは、作者の人間を観る目の確かさと、人間を信じているという強い思いがあるからかも知れません。心に残る今年の一冊となりました。 (店売事業部 中村努)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
次のページへ
|
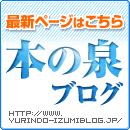
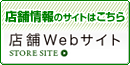
 クリック
クリック