| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス |
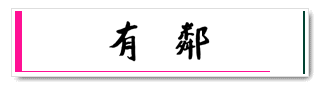
| 平成12年9月10日 第394号 P3 |
|
|
|
| 目次 | |
| P1 P2 P3 | ○座談会 氷川丸・70年の航跡 (1) (2) (3) |
| P4 | ○鎌倉彫 薄井和男 |
| P5 | ○人と作品 米沢富美子と『二人で紡いだ物語』 藤田昌司 |
|
|
|
| 座談会 氷川丸・70年の航跡 (3)
|
|
|
|||
| 細野 |
この時、一等はフルブライト(人物交流によって他国との相互理解を深めるために、一九四六年に米国で発足した奨学金制度)の留学生で満員で、一般の人は乗せられないほどでした。八十人全部。 |
||
| 金澤 | フルブライト用に改装したんです。フルブライト委員会から学生を運んでほしいと言われて、一等の公室(船室以外の公共のスペース)の一部をアメリカンモダンスタイルに改装した。結局、二千五百人ぐらい運びました。帰りはアメリカの交換の留学生が乗ってくる。
|
||
| 細野 | そのときに、起点の神戸、名古屋、横浜、シアトル、終点のバンクーバーの各港で航路再開のレセプションを
したのですが、シアトルでは日本からの移民一世の人たちが続々と来て、船の中は黒山のような人になった。バンクーバーでもそうでした。なつかしがって、その一航海は大変でした。私はそのときは食堂の監督をしていました。
|
||
| マナーを鍛えられている客船乗り
|
|||
| 篠崎 | 氷川丸で司厨員というのはどんな訓練を受けていらしたんですか。 |
||
| 細野 | 普通のサービスの基本などで、いわれたことは人間性ですね。 |
||
| 竹澤 | 私は航海士ですが、マナーは厳しいんです。貨物船に乗っている者は行儀があまりよくないから、客船に乗せないんです。例えば甲板員が外のガラスを拭くとき、客室内をちょっとのぞくだけでも大変なことです。マナーは客船に乗るときに鍛えられているから客船乗りは客船乗りと決められていたんです。
私たちだって風呂場が部屋にあるわけじゃないし、部屋はボートデッキですからお客さんとは関係ない所ですが、すぐそばにあるお風呂に入るにも、くつ下をはき、靴をはいて行くんです。我々航海士でもそれほどですから、ボーイさんなどは徹底的でした。 |
||
| 金澤 | 吉月さんも、氷川丸に乗られた十四日間、甲板部や機関部の人たちとは余り会われなかったでしょう?
|
||
| 吉月 | 船長さんとはよくお会いしましたね。私たちは三等Aでした。宝塚は上級生順が厳しいんです。それは当然のことで、それこそが宝塚の素晴らしい伝統だと誇りに思ってます。
|
||
| 細野 | 三等はAとBがあって、Aは食事が洋食、Bは和食なんです。二等はなくて一等と三等なんです。
日本人のお客さんは和食が食べたくなるから、一等の人が下の三等に行って交換してもらうということもありましたね。それ以外に、すきやき、てんぷら、寿司、刺し身などを週一回ぐらいメニューに出していました。 私たちは朝の七時にエンカイリー(フロント)をあけて、夜の十一時までボーイさんと二人で勤務するんです。 | ||
|
|
|||
| 吉月 | バンクーバーに着いたとき、今思うとおかしいですが、戦争をした国に来たと思いました。期待や不安で複雑
でした。昭和三十四年ですけどね。 一等社交室はフリーでしたから、三等にもかかわらず、ここらをグルグル遊び回っていました。あのころアメリカに行くってすごかったじゃないですか。それこそまだ自由化されていないときでしたから。だから選んでもらおうと思って行きたい行きたいって大変だったんです。 お食事がおいしかったですね。四十一年たってもまだ、あのおいしさが忘れられないのは、ハーフグレープフルーツ。グレープフルーツなんて当時は聞いたことも見たこともないでしょう。あれは貴重な味でしたね。半分に切った上にお砂糖をかけてね。 ある日、船がものすごく揺れたんです。朝、食事の時ドラが鳴るんですが、だれも行かないんですよ。外を見たら、今の都庁ぐらいの高さにグワーッと水面がえぐれているんです。ここに入ったらどうしようと思って。でも私は食いしんぼうだったので壁をつたって、親友と二人で食堂に行った。するとボーイさんたちがウワーッと万雷の拍手で迎えてくれました。お客は私たち二人だけ(笑)。ですから氷川丸と聞くと胸が痛いぐらいなつかしいんです。 |
||
| 篠崎 | 氷川丸で舞台の練習もしていらしたんですか。 |
||
| 吉月 | やりました。毎日デッキでお稽古をしました。そのときは全部日本ものですから、みんな浴衣を着てやるんです。運動がてらにやっていたんですが、雨が降るとテントを張って。乗船されていた方は見物していらして退屈しのぎによかったみたいです。
船を降りたくなかったですよ。アメリカ全土を歩いたのもよかったんですけど、この船の印象はすごいですね。 |
||
| バンクーバーに着く前日、エンジンルームまで和服で挨拶に
|
|||
| 金澤 | 航海日誌を見ますと七月二十六日に出帆して、二十八日には気温がもう十四度ぐらいになっています。それで一日休んだだけで、稽古を始めたそうですね。
|
||
| 吉月 | 出港のときは暑かったですね。振り袖で日本郵船の本社にご挨拶に行って乗ったんですが、船に乗るとすぐさま脱ぎ捨てて、デッキでみんなでお握りを食べたんですよ。私の母が心を込めてつくってくれたんです。
|
||
| 金澤 | その航海に乗船していた船員の話を聞きますと、バンクーバーに着く前日に、さよならパーティーをやったそうですが、そのときも皆さんは和服を着たままでエンジンルームまで挨拶に回られたそうです。
|
||
| 吉月 | ほとんどずうっと着物でしたから。 |
||
| 金澤 | でも皆さん、よくおなかが空いたと見えて、夜になるとギャレー(料理場)にやってきたという話も聞いたことがあるんです。夜食をつくってもらいに。
|
||
| 篠崎 | アメリカにはどのくらいいらしたのですか。 |
||
| 吉月 | 四か月おりました。ニューヨークではメトロポリタンオペラハウスで一か月公演しました。それからワシントン、テキサス、ニューメキシコまで、全部回りました。
アメリカは本当にショックでしたね。カフェテリアとかハンバーガーショップとか、初めてで。それに、おいしくて。 帰りはシアトルから日航のチャーター機でしたが、これが墜落するところだったんです。テレビに一人一人の顔写真が出て「日航機遭難」とテロップで流れたそうです。窓から外を見たら火花が散っている。「あら、きれい。火花が飛んでる」って。羽田では着物で降りますので、みんな着物を着ていたんですが、そのうち「でも、おかしいんじゃない。エンジンが止まってる」って。でも無事に羽田に着きました。 |
||
| 往復切符で日本旅行をする外国人
|
|||
| 篠崎 | その頃のお客さんはどんな方だったんですか。 |
||
| 細野 | 日本人は一世の人ぐらいで、あとは外国人でしたね。切符を往復買うんです。氷川丸は四月に一か月間、神戸でドックに入るので、その間に日本を旅行して、帰りもまた同じこの船で帰る。当時、三等Bが片道三百何十ドル(約十四万円)でした。
アメリカに渡った日本の戦争花嫁の人の里帰りなども多かったですね。里帰りできるのはいいほうだったらしいですね。また、移民一世で、何年もたって自分の故郷に死ぬ前に一回行きたいという人もいましたね。 |
||
| 金澤 | 戦後は、昭和二十八年にシアトル航路に貨客船として復帰して、昭和三十五年十月に引退するまで四十六航海しています。その間の乗客数は一万五千八百人です。
|
||
| 細野 | 一万人目がカナダ大使館に勤務していたミス・レリアン・コーさんで、プロムナードデッキを全部飾りつけて、ケーキをつくったり記念品を贈ったりしてお祝いしたんです。昭和三十三年です。
|
||
| デザインコンペで選ばれたマーク・シモン商会のアール・デコ
|
|||
| 篠崎 | 今お話を伺っている一等社交室もそうですが、アール・デコ様式の内装は、旧朝香宮邸、今、庭園美術館になっていますが、そこと糖業会館と氷川丸の三つしか日本にはないそうですね。
|
||
| 金澤 |
氷川丸を建造するときに、特等公室、一等社交室をはじめとする一等の公室の内装についてコンペをやり、世界中に室内デザインを求めたわけです。その結果、フランスのマーク・シモン商会が選ばれアール・デコ様式が採用されたわけです。 |
||
| 篠崎 | 全部フランスから運んできて、日本で組み立てたそうですね。 |
||
| 金澤 | はい。氷川丸と秩父丸(後の鎌倉丸)がアール・デコでした。 |
||
|
|
|||
| 篠崎 | 日本において氷川丸は代表的な船舶ですよね。だから日本の海運史に占める氷川丸のポジショニングは大変なものがあるんでしょうね。
|
||
| 金澤 | と思いますね。まず七十年という歴史と、それから昭和という時代を生き抜いた。その間に豪華客船の時代、それから病院船の時代は相当な数の傷病兵を運んだ。そのあとの引揚輸送、戦後の復興をかけての食料や原材料の輸送。それから、また華やかなシアトル航路への復帰。これだけいろいろな人たちにかかわった船はないと思います。
|
||
| 篠崎 | 昭和の歴史そのままですね。 |
||
| 竹澤 | ただ、残念なのは船体が客船らしくない風情なんです。というのは、普通客船は二層、三層も高い。ところが氷川丸は北米航路だし、貨客船なので貨物も運ぶわけです。風波が強い冬の北太平洋を横断するためには船体の強度の問題もあるので、北米航路の船はみんな低いんです。その点は残念に思います。
|
||
| 国際条約発効前にその精神を考慮して建造される
|
|||
| 金澤 |
まず第一に、タイタニックが明治四十五年(一九一二)四月に大西洋で氷山と衝突して沈没し、たくさんの人命が奪われました。これを契機として、国際会議で、海上における人命の安全のために船舶の設備や構造について検討され、一九一四年(大正三)に条約がつくられます。 しかし条約締結の前に第一次世界大戦が始まったので、大戦終結後、あらためて内容を検討しなおして一九二九年(昭和四)に新しく条約が作成され、一九三三年(昭和八)に発効します。その条約を日本で国内法に取り入れたのは昭和八年です。氷川丸はその前につくられましたが、条約の精神をある程度取り入れて建造されました。 |
||
| 船体の外板の厚さ骨組の頑丈さにディーゼルエンジン
|
|||
| 金澤 | 二つ目は、船体の外板が厚いんですよ。 |
||
| 細野 | 私が乗っているときバンクーバーで衝突されたことがあるんです。普通だったら穴があいて浸水するところだったのに、鉄板がへこんだだけで済みました。それだけ厚いんです。
|
||
| 金澤 | 通常は、このクラスの船ですと外板の厚さが十一ミリだったそうですが、北太平洋が常用航路になるので、十五ミリにした。それに加えて、縦通材を太くして数も多く入れた。人間で言えば肋骨みたいなものです。
|
||
| 竹澤 | それと、エンジンがディーゼルということも画期的なんです。 |
||
| 金澤 | デンマークのB&W(バーマイスター・ウエイン)社のエンジンを装備した。 船体の外板の厚さ、それから骨がしっかりしている。そのうえ法律をある程度先取りしてつくった。そういうことで、触雷しても少々の浸水程度で生き残ったんですね。 燃料も重油です。石炭焚きの船は石炭を積むスペースだけ貨物が積めないし、人手も要る。焚いた石炭がらも捨てなけれなならない。重油はそれが必要ない。ですから、当時としては、この船にあらゆる工夫を凝らし、いろいろな設計思想を取り入れたんですね。そういう点でも歴史的な船なんです。 |
||
| 篠崎 | お話を伺っていると船という一つの物ではあるんですけど、何か魂があるみたいな感じがしますね。
|
||
| 金澤 | 病院船時代の人たちは氷川丸会をつくっているんです。戦後、引揚船時代に乗船された乗組員や病院関係の方たちもまた、氷川丸会をつくっている。『ホトトギス』の昭和二十四年二月号によりますと、北海道に吟行した高浜虚子一行の方がたも氷川丸会をつくっているんですね。
|
||
| 篠崎 | みなさん、乗ったときの思い出がすごくあるんですね。 |
||
| 吉月 | そうですね。それと戦火をくぐり抜け、今も凛とした美しい姿の氷川丸に、いとおしさと感謝の気持ちがいっぱいです。“宝塚わが心のふるさと”ですが、氷川丸もわが心のふるさとです。
|
||
| 篠崎 | 竹澤さんの『病院船氷川丸を讃える歌』も拝聴したいですね。 |
||
| 竹澤 | 作曲はサロンボーイだった田中元彦さんです。いい曲なんですよ。 |
||
| 金澤 | 日本郵船歴史資料館では「竣工七十周年記念 氷川丸」展を十二月十七日まで開いていますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。
|
||
| 篠崎 | きょうはどうもありがとうございました。 |
||
| たけざわ あつむ |
| 一九二三年東京生れ。 |
| ほその しんざぶろう |
| 一九二〇年鎌倉生れ。 |
| よしづき あけみ |
| 一九三三年東京生れ。 |
| かなざわ かんじ |
| 一九三七年長野県生れ。 |