| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス |
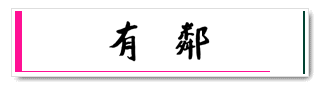
| 平成14年9月10日 第418号 P1 |
|
|
|
| 目次 | |
| P1 P2 P3 | ○座談会 グレート=ブックス=セミナー (1) (2) (3) |
| P4 | ○ヨコハマ 私の好みに合った街 バーリット・セービン |
| P5 | ○人と作品 高野和明と『グレイヴディッガ−』 藤田昌司 |
|
|
|
| 座談会 グレート=ブックス=セミナー (1)
−横浜市中央図書館の新たな試み− |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 『グレート・ブックスとの対話(ダイアローグ)』 松田義幸、須賀由紀子、江藤裕之:著 (財)かながわ学術研究交流財団(直取扱):刊 1,000円(5%税込) |
| はじめに |
|||||
| 篠崎 |
そこで本日は、インターネットなどを通じて、手軽に情報を得ることができる時代に、あえてこうしたセミナーを始められた目的や具体的な内容をご紹介いただきながら、その成果などについてお話を伺いたいと存じます。 ご出席いただきました梅田誠様は医学がご専門で横浜市立大学長などを歴任され、現在は横浜市中央図書館長でいらっしゃいます。 後藤英司様は横浜市立大学医学部教授でいらっしゃいます。同大学では、横浜市中央図書館と協力して「グレート=ブックス=セミナー」を開催されていますが、先生は大学で医学教育などを担当され、このセミナーの推進者のお一人でもいらっしゃいます。 宮原忍様は、産婦人科医として活躍された後、東京大学医学部保健学科、横浜市立大学看護短期大学部教授をお務めになり、現在は、日本子ども家庭総合研究所母性保健担当部長(社会福祉法人・恩賜財団母子愛育会)でいらっしゃいます。 以上のお三方はセミナーを進行させていくモデレーター(進行役)として、この活動を推進しておられます。 増田節子様は、横浜市西区にお住まいで、熱心なセミナー参加者のお一人です。 |
||||
|
|
|||||
| 篠崎 |
まず、「グレート=ブックス=セミナー」はいつ頃からはじまったのですか。
|
||||
| 梅田 |
「グレート=ブックス=セミナー」はアメリカの大学で取り入れられて非常に盛んになっているセミナーなんですが、モーティマー・アドラー博士を抜きにしては語れません。
アドラー博士は一九二○年にコロンビア大学に入り、二一年にコロンビア大学のアーキンス先生の古典読書に出会うんです。古典というのは普遍的価値があるので読みつがれているわけですが、アドラー博士は、そのじっくりと読むセミナーに共鳴し、古典の読書がいかに大事かということを知るわけです。それで、アドラー博士は古典読書にどっぷりつかっていくわけですが、それがさらに発展するのは、一九三○年に、ハッチンスという人が三十歳でシカゴ 大学の学長になるんですが、その前から知り合いのアドラー博士を招いて、シカゴ大学で「グレート=ブックス=セミナー」を開講していた。 別の資料によると、ハッチンス学長が学生と一緒にセミナーで意見を述べ合うということで非常に有名になり、そういう勉強の方法がすごくいいということで、それ以後ずっとアメリカの大学に行き渡った、とあります。それで、一九四五年以降、またピークを迎えるわけですが、一番のピークは一九六五年頃と書いてありました。大学の一般教養がすべて「グレート=ブックス=セミナー」を取り入れるという形、一般教養のアメリカの原形みたいなものになっていったようです。 |
||||
生涯教育やエグゼクティブのセミナーにも
|
|||||
| 梅田 |
アドラー博士はアメリカの大学で、「グレート=ブックス=セミナー」を広めましたが、大学以外でも、卒業生に対する生涯教育やエグゼクティブのセミナーもやっていて、それから初等教育、高校生とか中学生のセミナーも大事だとしている。
喜多村和之『大学淘汰の時代』(中公新書)に書いてありましたが、結局、その後、「グレート=ブックス=セミナー」を中心にした大学の一般教養教育は、それだけでは成り立っていかないという風潮も出て、別の方向も出てきて、今は交錯している状態のようです。 でも全面的な古典だけではなくて、少し修正した形で本をじっくり読むという方向はアメリカでは続いています。 |
||||
| 篠崎 |
欧米の場合は、グレート・ブックスの典型的なものは、やはりギリシャ哲学なんでしょうか。
|
||||
| 梅田 |
いや、ギリシャ哲学だけでなく、ルネサンス期の本もたくさんあるから、そういうのも含めての古典です。
|
||||
| 後藤 |
基本的にはホメロスが最初にあって、プラトンやアリストテレスとか、その辺が並びます。でもルソーとか、ベンサム、ミルらのフランスやイギリス哲学も入っています。
|
||||
| 梅田 |
読み継がれてきたのは、それだけ普遍的な価値があるからで、それを勉強しない手はないというのが、アドラー博士たちの古典を読む一つの考え方のようです。
|
||||
|
|
|||||
| 篠崎 |
梅田先生が「グレート=ブックス=セミナー」を中央図書館で始めようと思い立たれたきっかけは…。
|
||||
| 梅田 |
『グレート・ブックスとの対話』を書かれた松田義幸先生に、勧められたのです。かながわ学術研究交流財団(K−FACE)という長洲一二前知事を中心につくられた財団で、その学術研究の中にグレート・ブックスを広めるための研究会があり、松田先生が主宰しています。
僕は誘われてそこでのゼミナールに出席し、「いいですね」と言ったら、「図書館でやって下さい」と。だけどなかなかできなくて。それと図書館より大学でやったほうがいいんじゃないかと、初めはそう思っていたんです。たまたま病院で医療事故があり、「倫理ですよ。それでやろうよ」と後藤先生に話しかけたら、医学教育のコースでやりましょうと同調してくれた。 |
||||
いい本の提示をして読書離れを止める役割
|
|||||
| 篠崎 |
図書館の試みとしては日本で初めてですね。図書館活動の大きな柱の一つに育てられるご計画でしょうか。
|
||||
| 梅田 |
一方、「図書館は、蔵書を評価しないで均等に並べている」という議論があります。司書は、全部並べて全部出すのが図書館の役割であると。 本の良い悪いは言わないと言うんです。僕にしてみれば、いい本はやっぱりいい本だから、がっちり読まなきゃいけないのではないかと。 もう一つは、今の読書離れをどうしたらいいか、とくに中高生の読書離れにどう対処したらいいか、考えていました。 その三つぐらいのことを考えまして、じっくり本を読むのも大事ではないかと。その前に、こんなにいい本がありますよと、まず提示をすることが先ですから、それでいい本を示して読んでもらう。特に学生に読んでもらうのが 目的だったんです。しかし、なかなか問題がありました。 |
||||
| 篠崎 |
アドラー博士の思想を基にした『グレート・ブックスとの対話』の著者、松田先生のお勧めを発展させたんですね。
|
||||
| 梅田 |
K−FACEで、毎年、東京近辺の学生に呼びかけて、セミナーを開いています。そこではアドラー博士のカリキュラムをそのまま日本へ持ち込んできて、ギリシャ哲学から始めています。本も同じにして、単に、日本語に変えてやるというプログラムでした。それを、公共図書館でおこなうことで少し独自な工夫を凝らして始めました。
|
||||
| 篠崎 |
アドラー博士の本は『本を読む本』(講談社学術文庫)が翻訳されていますね。
|
||||