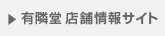【Book】藤野千夜「夏の約束」復刊に寄せて

それぞれの日常
いろんな幸せのカタチ。
「夏になったらキャンプに行こう」
”約束”ってちょっと面倒だけど
みんなを繋ぐ”希望”でもある。
小説家・藤野千夜
その優しい眼差しの、原点。
「夏の約束」は、この分断の時代にあって、
それぞれの孤独を感じる人たちに
小さな希望を持たせてくれる “願い”の物語になるはずだ。
そう信じてこの夏、私は講談社さんに
リクエスト重版の企画を持ち込んだのだった。
STORY STORY YOKOHAMA
名智理
藤野千夜『夏の約束』講談社文庫¥704tax in
オンラインショップはこちら
https://story-yokohama.com/items/687605e98c0c271430b21e32



「ボクは、マルオになりたかった」
~藤野千夜『夏の約束』(講談社文庫版)重版に寄せて~
「夏の約束」が単行本として発売されたのは2000年の2月の事。
第122回の芥川賞を受賞したときだ。ボクは大学生協で購入した。

この物語は、ゲイのカップルの会社員マルオと編集者ヒカルを中心に、ヒカルと幼なじみで売れない小説家の菊江、友人のOL岩淵のぞみ、トランスジェンダーの美容師たま代……少し“ふつう”からハズれた人たちの日常を軽やかに描いた群像劇だ。
「夏になったらキャンプに行こう」というたま代の誘いは、よくある友だちグループの話のように、いいねと同意されながらも一向に実現することなく先延ばしにされている。もちろん悲観的なことではなく、ちょっと先の楽しい(けど少しめんどくさい)ふんわりとした約束として皆の間にぼんやりと漂っているのだった。
マルオは『身長一七五センチ、体重九五キロ。先月、会社の健康診断で太りすぎを警告された』総務部総務課に勤めるゲイの男性だ。『もはやマルオには、太っていない自分というものがあまり想像できなかったし、太っていない自分が果たして幸せかどうかもわからな』いのだった。
マルオは中学生と高校生のころ、同性愛を理由にいじめにあった。そういった背景から、『美味いものでも不味いものでも、脂っこいものでもさっぱりしたものでも、しばらく駄目だった鶏肉(鶏小屋に閉じ込められたから)でも、マルオはとにかく食べまくった。日々皮下脂肪をため込んで行き、弾力あるからだを構築しなくてはならない。そうしなければ、生きていけないような気が』していたからだ。(大人になった今はそうは思っていないらしい)
一方、ボクはといえば、そんないじめにはあったことはないけれど、静岡の片田舎から上京してきて、なかなか東京の暮らしに馴染めず、友だちもあまり出来なかった。独りぼっちで、何もできない、まだ何者でもない自分と、目の前に広がる漠然とした未来に怯えた。もちろん、マイノリティのひとりとして生きていくことを選択する前の話だ。
そんなときに、「夏の約束」という小説に出会う。ふだん、登場人物に感情を入れ込むような共感的な読書をしたことがなかった自分が、唯一、「わかるなぁ」と思ってしまったのが、マルオという人物の心理描写だった。
おかしなことかもしれないが、ボクももっと太らないと自分を守れない、強く生きられないと思ったことがあった。そんな学生時代はあっという間に行き過ぎて、社会に出て、早、二十数年が経った。ボクはいま130kgも体重がある。よもやマルオを超えてしまうとは誰が予想しただろうか!それほどまでに自分を皮下脂肪で守らなければと思い悩んでいたかというと、もちろんそんなことはなくて、途中からは不摂生な生活と年齢と共に痩せにくくなっていただけなのであって、文学的な要素は一切ない。もちろん、悲しんでもいない。人生、そんなものだ。
でも学生時代、孤独だった自分が「夏の約束」という小説に出会って少なからず救われたのは確かだと思う。文学部の卒業論文のテーマに藤野千夜を選んだくらいだから、その時期は初期のマイノリティを扱った作品群にのめりこんでいたのだと思う。少し“ふつう”からハズれた人たちの日常が決して特異でもなければ悲観的でもない、という意味において。
今でこそ「多様性」というワードは、社会に当たり前に浸透している(正しく理解されているかどうかは別)けれども、2000年当時、「夏の約束」のようにマイノリティの“日常”を軽やかに、しかもリアリティをもって取り上げることは、文学的には先進的であったと思う。その貴重な作品をこの令和の時代に、「紙の本」として再び復刊すること。“書店という場所”で誰もが出会えるカタチにすることには、ちゃんと意味があるように思う。
「夏の約束」は、この分断の時代にあって孤独を感じるすべての人たちの、漠然とした明日に小さな希望を持たせてくれる “願い”の物語になるはずだ。
実は今回、Wカバー仕様にすることになって、ならばその裏面にちょっとしたエピローグを書き下ろしていただくのはどうだろう、と提案したところ、藤野さんが快諾してくださった。夢みたいだ。
「夏の約束」が25年の時を経て動き出したのだった。
『マルオがうなずくと、ヒカルは天井を見上げるように顎を大きくしゃくった。
それからコックリさんにでも訊ねるみたいな抑揚のない調子で、
来年私たちはみんなでキャンプに行けるでしょうか、と言った』
有隣堂
STORY STORY YOKOHAMA
名智理