| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス |
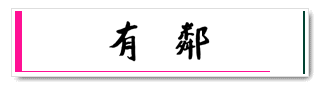
| 平成14年1月1日 第410号 P2 |
|
|
|
| 目次 | |
| P1 P2 P3 | ○座談会 城山三郎と戦争文学 (1) (2) (3) |
| P4 | ○アトムの向こうを考えよう 瀬名秀明 |
| P5 | ○人と作品 西村京太郎と『焦げた密室』 藤田昌司 |
|
|
|
| 座談会 城山三郎と戦争文学 (2)
|
| 藤田 | そうです。新聞記者も現場に行けと言うし、刑事も現場百回と言うし、作家もそうですね。やっぱり現場を踏まないと本当の臨場感のある情報は……。
|
||
| 城山 | 何にもなくても、そこへ行って空の雲を見たっていいんです。それが違うんですよね。 |
||
| 藤田 | 取材で、戦争体験を語る人が非常に少なくなってきた、ということはありませんか。 |
||
| 城山 | ええ。でも、今ならまだ書けますけどね。でも周辺の事情や歴史の動きなどを調べるのに、今からは、パソコンやインターネットを自由に使えないとだめですね。
|
||
| 最初と最後の特攻隊員となった二人が主人公
|
|||
| 藤田 | 『指揮官たちの特攻』の主人公の二人の大尉、中津留達雄と関行男は海軍兵学校の昭和十六年の同期生です。一方は最初の神風特攻隊員になり、一方は天皇の終戦の玉音放送があったあとに宇垣纏長官を乗せて沖縄に飛び立った、つまり日本最後の特攻隊員だった。実に対照的な指揮官を書かれたわけです。
二人は、特攻隊としての散り方も対照的ですが、生き方も人生そのものも非常に違った性格ですね。 |
||
| 城山 | そうですね。 |
||
| 藤田 | 片や非常に優しくて愛妻家で、片や家庭的にはやや複雑であるということで、これは、ほとんど虚構なしにお書きになられたのですか。
|
||
| 城山 | はい。人名を書くときは事実で、調べて書いています。二人の性格が対照的だということを予想していたわけではないんですが、調べていくと、そういう性格に育った理由がわかってきます。片方は非常に温和な性格で、片方は非常に激しい性格。
|
||
| 藤田 | しかし、二人とも二十三歳で、妻をめとってまだ間もない。だから、あわれというも愚かなりで、本当にかわいそうな人生ですね。
|
||
| 城山 | かわいそうですね。僕らは結婚していなかったから観念的でしたが、家庭生活とか、結婚生活を知った人にとっては辛かっただろうと思いますね。
|
||
| 米軍キャンプを避けて岩に突っ込んだ中津留大尉
|
|||
| 藤田 | 最初の特攻隊になった関さんのほうは、戦果は確認されているわけですね。 |
||
| 城山 | 関大尉の指揮する五機はレイテ沖で航空母艦一隻を撃沈し、もう一隻を炎上撃破、巡洋艦一隻轟沈という華華しい戦果をあげたことになっています。ただ、米軍側の記録とは少し違っているんですが。
|
||
| 藤田 | 中津留さんのほうは沖縄の敵艦隊を攻撃するということで、出撃する。 |
||
| 城山 | 八月十五日の夕方、急降下爆撃機の彗星に乗り込んで沖縄の伊平屋島に行き、軍事拠点を避けて、岩にぶつかったり、田んぼに突っ込んだんです。
|
||
| 藤田 | 戦果をあげる目的があったんですか。 |
||
| 城山 | 戦果をあげないようにしたんです。終戦ということが途中でわかってきた。だからもし軍事拠点に突っ込んでいたら、また戦争になる。とにかく突っ込んではいかんということで避けるんです。
|
||
| 藤田 | 終戦になってからの突入とは悲壮ですね。 |
||
| 城山 |
途中に敵の戦闘機も敵艦もいないし、米軍キャンプでは煌々と明かりをつけ、勝利を祝うビア・パーティが行われている。命令にうなずいたふりをして左に避ける。そうすると、二番機とは連絡はとれないけれど、一番機の動きに従えというものすごい訓練をそれまでに随分している。 一番機の動きを絶えず見ているわけですから、急に左に逃げたということは、ここを避けるんだなということを二番機の機長は読み取った。けれども、自分はもう避けられない。それで上げ舵は簡単ですから、上げ舵を引いて、米軍キャンプを越えて向こうの田んぼに落ちてしまったということだと思います。 当時の部下たちが言うのには、爆撃機を使っての編隊飛行は、戦闘機ならともかく信じられないぐらい非常に危険なんだそうです。ともかく敵の戦闘機を切り抜けるためには、戦闘機同様に戦わなければいけないということで、ものすごく激しい訓練をやっていた。ですから、海軍にいた人たちも飛行隊の人も「その推理は正しいでしょう」とみんな言っていました。 |
||
| 一番ジレンマを感じた指揮官
|
|||
| 藤田 | 二人の指揮官を主人公にされた意図は、どういうところにあったんですか。 |
||
| 城山 | 僕たちは年齢的に兵士たちに近いのですが、兵士たちは言われた通りに動くよりしようがないわけです。自分の判断の入る余地はないし、また、若いといろんなことを考えないで済むところがありますね、家庭がなければ。
ところが、指揮官ぐらいの年齢になると家庭があるし、自分で判断ができる。この命令はおかしいと思っても、中間管理職はそれに従っていかなくてはいけない。あるいは逆らう場合もあり、そういう意味で、中間管理職である指揮官は一番ジレンマを感じたと思いますね。 |
||
| 藤田 | しかも、海軍兵学校出身で、海軍では一番中核になっているリーダーですね。 |
||
| 城山 | そういう誇りみたいなのもあるでしょうね。 |
||
| 藤田 | 予備学生だったら、こういう小説にはならなかったでしょうね。 |
||
| 城山 | 予備学生でも随分突っ込んだし、立派な遺書を残している人もいますが、海兵の出身者には予備学生にない使命感があったでしょうね。
|
||
| 藤田 | 組織そのものに対する使命感でしょうね。 |
||
| 城山 | そうですね。それから自分の今までの生涯の締めくくりとして、こういう死に方がいいかどうかということを、予備学生の人は考えなくても済むんじゃないか。
|
||
| 藤田 | 中津留大尉がそういう突っ込み方をしたのは、組織に対するだけではなく、自分の人生に対する責任を取ったという感じがしますね。
|
||
| 城山 |
アメリカでは参謀という佐官クラス、中佐とか大佐とかでも、慣熟訓練と言って操縦に絶えず慣れるように時々みんな飛んでいます。いつでも第一線に出られるように。ところが日本は、参謀クラス、佐官になると、もう飛ばないんです。地上にしかいない。それと、頭だけで「やれ」とかいうだけで、佐官はほとんど死んでないし、参謀クラスはみんな行かない。 |
||
| 藤田 | 読者の反響はいろいろありましたか。 |
||
| 城山 | たくさんありましたね。 |
||
| 藤田 | 一般に、男の読者は手紙は書かない。しかも、この本の読者は恐らく、自分の読後感なんか照れくさくて書かない世代だと思うんです。
|
||
| 城山 | 数えてませんが何百通でした。女性の方も二、三割はありました。若い人のもありますが、大体が戦争体験のある年配の人で丁寧な詳しい手紙をくださっている。本当は返事を書かなくてはいけないのに、ちょっと勘弁してもらっているところです。
読者の皆さんは普通に生活をし、普通に会社勤めを終えて、悠々と暮らしているみたいだけど、皆さんが戦争を考えて生きておられるということがしみじみわかりました。 |
||
|
|
|||
| 藤田 | 城山さんが戦争文学にこだわられるのは、ご自身が昭和二十年五月から八月まで、海軍特別幹部練習生として軍籍を持たれた。つまり、少年兵として訓練を受けた体験が根底におありだからだと思うんですが、もともとは予科連志望だったんですね。
|
||
| 城山 | いや、最初は陸軍の予科士官学校を受けたんです。学科に通った人を埼玉県の朝霞にあった本校に呼んで、身体精密検査と面接があった。
|
||
| 藤田 | 学科に受かったわけですか。 |
||
| 城山 | ええ。朝霞へ行って二泊か三泊しましたかね。そして一つは体重不足。中学生時代からミイラというあだ名があったんです。英語でミラーと呼ぶところをミイラと呼んだから付けられたんだけれど、実際、それぐらいやせていたし、心臓に何か異常があるということで帰された。
|
||
| 藤田 | 特別幹部練習生のほうは通ったわけですか。 |
||
| 城山 | そっちはね。でも、そっちは人数さえ集めればいいということだったんでしょうね。ともかく特攻要員だから、そんな長生きするわけじゃない。片一方は士官としてずうっと長く軍隊に勤務するわけですから、やはりちゃんと採らなくてはいけない。特攻で一番使いやすいのは結婚前の、少年よりは青年と言いますか……。
|
||
| 藤田 | 一言で言えば、特攻要員の養成ですか。 |
||
| 城山 | だって一万人とか採ったわけでしょう。当時、軍艦なんか一隻も動かない状態です。そんなときに中堅幹部の大量募集をやったって意味がないんだから。
|
||
| 藤田 | 七つボタンですか。 |
||
| 城山 | 七つボタンで、桜に錨。襟章が予科連は翼なんです。僕らの場合は桜になっている。それだけの違いで、服装は予科連と全部同じです。
|
||
| 『大義』の純粋さに打たれた若者たち
|
|||
| 藤田 | 士官学校や海軍特別幹部練習生を志願されたときの思想的な背景は『大義』という杉本五郎の本だと書かれておりますが、当時『大義』は中学生の間ではベストセラーだったわけですか。
|
||
| 城山 | と思いますね。相当読んでいましたよ。 |
||
| 藤田 | 要するに忠君愛国を説いている。 |
||
| 城山 |
戦後、奥野健男さんなんかも疑問を持って調べたら、その伏せ字の箇所は、大陸に行っている皇軍は暴行略奪をほしいままにしている。あれは皇軍ではない。そういったことが書いてあったらしいんです。 杉本五郎はそういう正義感の人で、純粋に思い詰めて書いたから、僕らに訴えてくるわけです。だから、軍は困った。読ませたいけど、そこを読まれたら困る。それで伏せ字で出したんです。軍は杉本五郎は要注意人物だ、忠君愛国を鼓吹するけれど、今の日本がやっていることは悪いと書いている。というので、最激戦地に飛ばされ、戦死するわけです。まあ死刑ですね。 若者はその純粋なものに打たれて、次から次へとみんな愛読していった。本当に魅力的な本だったんですよ。 |
||
| 藤田 | 私は『大義』は読んでないんです。田舎にいたのと、三年の年齢の差があったからかもしれない。
|
||
| 城山 | よかったじゃないですか。読んでいたらきっと志願していた。大変訴えかける本だから。 |
||
| 反対する父親が応召中に、母親が海軍へ行く判を押す
|
|||
| 城山 | じつは、僕の母方の祖父が尾張藩だけに出入りしていた畳職の棟梁で、一種の御用商人なんです。お城の近いところに住んで、その斜め向かいに竹中工務店の先祖にあたる大工の棟梁がいて、親しくしていたようです。公の仕事しかしないから、母親にも、何となく公の観念があって、多少僕に対して理解があったと思う。
母には三兄弟がいまして、長男は東京の駒場で書店をやったり、戯曲集の出版などをやっていましたが、三度召集され、結局、志を遂げずに亡くなる。次男は満州へ行かされて白衣の勇士となって帰ってくる。三男は幹部候補生かなんかで行って胸部貫通銃創で、ようやく命を永らえて帰ってきた。母の育った家庭はそういう空気だったから、 息子が行きたいといえば、行かせるべきだと。 |
||
| 藤田 | お父様は反対されたそうですね。 |
||
| 城山 | 大反対で理科系に行けと。ところが応召で父親がいないときに、母が海軍に行くことの判を押すわけです。
|
||
| 昇進のスピードが速いため訓練も制裁も激しい
|
|||
| 藤田 | 訓練は激しかったんですか。 |
||
| 城山 | 僕らがいじめられたのは、後から聞くといろいろ理由があってね。予科練は入ってある程度期間を置いて、水兵長、下士官になっていくわけです。僕らの場合は入ると同時に水兵長で、一年たつと二等下士官、二等兵曹、成績のいい者は一等兵曹ということがあり、予科連に比べて昇進のスピードが少し速い。だから、そういう人たちの憎しみを買って、制裁も余計激しかったんじゃないか。
それに戦争末期だったからみんな荒れていたんですね。戦地から帰ってきた下士官なんかは非常に荒れていた。目の前に軍艦が植木をいっぱい生やして泊まっているんですからね。何で植木かといと、飛行機から見えないように。といって、船をどこかに持っていく燃料もない。だから、呉から瀬戸内海にそういう船がずっとある。最初何だと思いましたね。 |
||
| 樫のこん棒で練習生を撲る上官
|
|||
| 藤田 | 幹部練習生の場所はどこにあったんですか。 |
||
| 城山 | 各鎮守府です。僕は広島県の大竹。名古屋は呉鎮守府だから大竹なんです。それから結城昌治さんは東京だから横須賀。結城さんは志願して入ったんだけど、入って一週間で身体検査で除隊になった。僕は本人から聞いたんですが、「あそこは本当に地獄だった。除隊になってよかった」と言っていました。
|
||
| 藤田 | 上官の制裁は手ではやらないんですね。 |
||
| 城山 | 手でやると向こうも痛いから「軍人精神注入棒」と呼ぶ、樫のこん棒でバーンとやるんです。手でやるときは向かい合ってお互いを撲らせる。撲り方の弱いやつは今度こん棒でまた撲るんです。
|
||
| 藤田 | 終戦になったときには、どんな気持ちでしたか。 |
||
| 城山 | とにかくピンとこないわけです。下士官たちが狂ったみたいに騒ぎ出して、アメリカが要求しているから、僕らをサイパンに送るとか言い出したり、僕らを精神的にいじめたり、それから犬を探してきて殺したり、自分たちが週末に行くクラブがあるんですが、そこへ基地の倉庫から米とかを夜に全部運び出して、私物にする。だから、最後の最後まで日本海軍もおかしかった。
|
||