| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス |
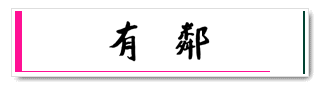
| 平成14年1月1日 第410号 P4 |
|
|
|
| 目次 | |
| P1 P2 P3 | ○座談会 城山三郎と戦争文学 (1) (2) (3) |
| P4 | ○アトムの向こうを考えよう 瀬名秀明 |
| P5 | ○人と作品 西村京太郎と『焦げた密室』 藤田昌司 |
|
|
|
アトムの向こうを考えよう |
|
|
|
世紀を越えて空前のロボット・ブームが続く日本
二〇〇一年にも夏から秋にかけて、関西と神奈川で「ロボフェスタ」という大きなイベントがあった。私も何度か足を運んだが、会場はいつも熱気に溢れていた。ホンダのASIMO(アシモ)が舞台に登場すると、とにかく観客の目は釘付けになる。 聞くところによると、ロボットのイベントは他のイベントに比べて観客の会場滞在時間が一・五倍ほど長いのだそうだ。展示をじっくり見て回っているわけで、ロボットに対する関心の高さがよくわかる。 ロボフェスタの最終日、横浜の会場で「知能ロボットコンテスト」が開かれ、私も審査員のひとりとして競技を観戦した。最近は各地でロボットコンテストが花盛りである。NHKの「アイデア対決・ロボットコンテスト」(通称ロボコン)をご覧になった方は多いと思うが、ロボット相撲やロボット水球など、実にさまざまな試合がある。なかでもこの知能ロボットコンテストは上級者向けといわれるものだ。
フィールドに散らばったテニスボールを、制限時間内に速くバスケットの中に収めるのだ。バスケットの位置を計算して正確に投げ入れるロボットや、投網の要領ですべてのボールを一気にとらえ、バスケットに機体もろとも落ち込んでゆくもの、ロボットが二手に分かれて一方がボールを端に寄せ、もう一方がそれを箱の中に収め、まるでブルドーザーのようにバスケットに流し込むものなど、バラエティに富んだロボットたちが集まった。 親子での参加もあったが、さすがに自律型ということで高度なプログラミングやロボット工学の技術を必要とするためか、シンガポールや韓国、イランなどからも学生がエントリーし、優れたロボットを披露して会場の注目を集めた。 面白いのは、会場でウケるロボットと着実に仕事をこなすロボットが必ずしも一致しないことである。黙々とボールを見つけてバスケットに運ぶロボットは、堅実に点数を稼ぐがどこか愛嬌に欠ける。審査員のひとりは「なんだか日本人の仕事ぶりを見ているみたいだね」と苦笑していたがその通りなのだ。一方、点数は低くても大技に挑戦するロボットは、観客から熱い声援と拍手が飛ぶのである。 ロボットは私たちと共に発展する「現在」の機械 私たちはロボットに何を求め、何を期待しているのだろうか? ロボフェスタの横浜会場では、脳外科手術を手伝うロボット・アームや、リハビリ支援ロボットも展示されていた。これまでのロボットイベントには見られなかった傾向である。おそらく近い将来、私たちはエンターテインメント以外に健康のパートナーとしてロボットたちと付き合うようになるはずだ。ここでは動きのミスは許されない。使いやすく、確実で、しかも親しみやすいロボットであることが必要となる。 いま私たちはASIMOが歩くのを見ているだけで満足できる。だがこれから私たちは、ロボットと一緒に暮らすことになる。ただ楽しいだけの関係ではない、そこでは生きて死ぬ苦しみや悲しみも共有しなければならない。いまのブームは、ロボットに対する期待感が漠然と膨らみ、その曖昧さ自体に未来を見ている状態である。 今後、いつかロボットに対する過度な幻想が破裂し、現実に呼び戻される時期が来る。そのとき私たちは生涯のパートナーとして本当にロボットと接することができるようになるだろうか。ロボットは決して「未来」の機械ではない。まさにいま私たちと共に発展する「現在」の機械なのである。 日本のロボット・ブームを語る際、よく手塚治虫の『鉄腕アトム』が引き合いに出される。日本にはアトムがいたからみんながこれだけロボットに親近感を抱くようになった、というのだ。欧米ではロボットに対する忌避感がいまだに強いという。人間の仕事を剥奪する存在であり、人間に似たものをつくることは神の意志に反する、と主張する人もいるそうだ。また欧米で制作されたロボット番組を観ると日本との捉え方の違いに驚く。まず登場するのがロボットの軍事利用の話題、 そして次は互いのロボットを破壊し合うロボット・バトル大会の様子である。日本人ならロボット同士が戦争することに嫌悪感を覚えるのではないだろうか。これは草木にも心が宿るという日本人の宗教観だけでなく、鉄腕アトムで刷り込まれた「ロボットは友達だ」というイメージが強いからだという。 これは確かに一面をとらえた意見だと思う。実際、いま日本でロボット工学を牽引している四〇代の研究者たちは、子供の頃にアトムの洗礼を受けている。アトムに憧れてロボット研究を目指したと公言する研究者も少なくない。また、アトムは誰もが知っているキャラクターなので、ロボットの機能を説明するとき引き合いに出しやすいというメリットもある。マスコミがアトムの話を振れば、大抵のロボット研究者はそれに乗るだろう。 アトムの姿をクリアに受けとめることができる若い世代
いろいろ調べてみたところ、どうやら昭和四十年生まれ前後でアトム体験は劇的に変化するようだ。それ以前の世代だと小さい頃にアトムを体験しており、むしろドラえもんは小さな子が読むマンガだと感じるらしい。また、若いロボット研究者と話していると、やはりアトムよりガンダムやパトレイバーといった乗り込み型のロボットアニメに対する思い入れのほうが強く、アトムの名前はあまり出てこない。 むしろロボット・ブームの中で、いまアトムのヒューマニズムが持ち上げられすぎているのではないか。実際、手塚のマンガを読んでみると、意外なことにアトムはほとんど人間社会に対して何もできない。無力の存在として描かれている。そればかりか、人間社会だけでなくロボット社会からも疎外された、極めて微妙な立場にいるのだ。そのためにアトムは悩み、葛藤する。 手塚治虫は生前、アトムについて「ロボットと人間のインターフェイスである」と語っていたが、そうであるならば余計に安易なヒューマニズムなど入り込む余地はない。子供時代にアトムにどっぷり浸からなかった若い世代こそ、手塚治虫の描いたアトムの姿をクリアに受けとめることができるような気がする。 ロボットにとって愛や正義、家族や友達とはなにか? いつか日本人は、本当のアトムの葛藤に気づくだろう。二〇〇三年四月七日は、手塚治虫が設定したアトムの誕生日である。これにあわせて、おそらくイベントプロダクションやロボット製作会社はいま着々とアトムづくりに励んでいるはずだ。アトムの誕生日にアトムの姿をしたロボットが登場する……きっと多くの観客を呼び込めるはずである。だが注意しなければならない。まだロボット研究は発展途上なのだ。 アトムは家族の愛情を欲し、正義とは何かと考える存在だった。いまのロボットは、愛や正義を考えるだけの人工知能を持ち合わせていない。アトムのようにしなやかに歩く機構も完成していない。アトムまがいのロボットしかできなかったとわかったとき、移り気な私たちはロボットに愛想を尽かしてしまうのではないか? ロボット・ブームは急速に萎んでしまうのではないか? それは何としても避けるべきだ。本当のロボット開発はそこから始まるのだ。 ロボットにとって愛や正義とは何か、家族や友達とはなにか? 難問である。その難問を解くのが二十一世紀だ。私たちはいまからアトムを超えたロボット社会を考えなければならない。 作家と読者が一体となって、アトムの次のロボットを考えてゆこう。物語の力で新しいロボット像を共有してゆくのだ。もうアトムは未来のものではない。私たちの目の前にやって来て、次の一歩を共に踏み出そうと待ち構えているのである。 |
せな ひであき |
| 一九六八年静岡県生れ。 |
| 著書『パラサイト・イヴ』角川書店1,470円(5%税込)、『ロボット21世紀』文春新書903円(5%税込)、 『ミトコンドリアと生きる』角川新書600円(5%税込)、ほか。 |