| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス | ■『有鄰』のご紹介(有隣堂出版目録) |
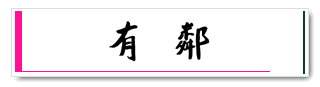
| 平成16年3月10日 第436号 P2 |
|
|
||||
| ○化粧坂の声 | P1 | 藤沢周 | ||
| ○座談会 外国人が詠む日本語俳句 | P2 P3 P4 | |||
| ○人と作品 | P5 | 綿矢りさと『蹴りたい背中』 | ||
|
|
||||
| 座談会 外国人が詠む 日本語俳句 (1)
|
|
||||||
| 左から原千代氏、宗左近氏、ドゥーグル・J・リンズィー氏、藤田晶司氏 |
|
はじめに |
|
| 藤田 |
日本の俳句人口は、今や一千万人を超えるといわれるほど盛況です。 万葉の時代から「言霊のさきわう国」といわれてきただけに、日本人は今、この、世界でもっとも短い詩といわれる文学に、日常性の中で関心を高めているといっていいでしょう。 また、この俳句は、今や日本人だけでなく、世界の人びとにも愛され、ブームになっているといわれます。 そこできょうは、外国の俳句にも精通していらっしゃる詩人の宗左近さん、オーストラリアのご出身で、日本で深海生物の研究に従事されるかたわら、日本語で数多くの俳句を詠まれ、句集もお出しになっておられるドゥーグル・J・リンズィーさんにお越しいただきました。 若手の詩人で俳人でもある原千代さんとともに、外国の方がつくる俳句について、また国際化のなかで日本の俳句はどうあるべきかなど、お話しいただきたいと思います。 |
◇俳句の伝統の上に新しい世界を開く |
|
| 宗 |
日本以外の世界中の国々、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、ほとんど全地球のスケールで、少なくとも30年来、HAIKUというのが猛烈な勢いで詠まれています。 驚くべき数のHAIKU人口がいるんです。 西洋のHAIKUは三行詩です。 中国でも漢俳と称した俳句をつくっていまして、やはり三行詩なんです。 つまりHAIKUと言うと、日本以外では三行詩なんです。 外国の多くの俳人が、三行詩という自分たちの新しい詩の形をつくって、必ずしも俳句の伝統に学んではいない。 もっと広がった、自由な俳句の受けとめ方をしているんです。 ところがリンズィーさんはそれとはちょっと違って、日本語の俳句を、日本の約束事に従って、日本の俳句の精神に則ってつくっておられる。 マブソン青眼[セーガン]さんというフランス生まれの方も、日本語の俳句をつくっています。 青眼さんは、雪梁舎でやっている「雪梁舎」俳句まつりで去年大賞をもらい、リンズィーさんは、おととしの「中新田詩の噴火祭」で中新田俳句大賞を受賞なさいました。 この二人はちゃんと俳句の伝統の上に乗っかって、しかも、新しく自分の持つ世界をつくろうとしている。 日本語で俳句を書いている外国人の方で、一番すぐれた方は、このお二人なんです。 |
ヨーロッパの詩の伝統を踏まえながら日本の文芸を超える |
|||
| 宗 |
リンズィーさんの句集『むつごろう』は、むつごろうという題そのものも日本的で、おもしろいと思うんですけれども、その中で僕がいいな、すごいなと思ったものが幾つかあるのでご紹介したいんです。 異人我れ陽炎を掴みつつある掌 陽炎を掴むという発想そのものが、もはや日本の文芸の伝統を超えている。 こういうとらえ方はないですね。 稲妻の光りて時間こはばりぬ 時間がこわばったと、時間そのものを単独に取り出して対象化した俳句の作品はかつてない。 機の窓に静脈のあと氷河見ゆ 自分の手の静脈が飛行機の窓に映っていて、その向こうの、あるようなないような氷河の流れ、静脈という見える脈と、氷河という見えにくいもの、静脈と氷河という離れたものが飛行機の窓という一か所に合体している。 全く新しい、日本にも余りなく、ヨーロッパの詩の伝統を踏まえていて、しかも、こうやって書かれると見事に日本化している。 というより、むしろ俳句化しているんです。 この3句には、芭蕉を先輩とする日本の俳句の精神がまっとうに受け継がれていて、大変まれな、僕の意見ですけれども、それ以後の日本の俳人がほとんど達成できない高さ、深さを持っている作品だと思うんです。 |
||
ヴェルレーヌと一茶の叙情を合わせ持つやわらかな作風 |
|||
| 宗 |
マブソン青眼さんも、『空青すぎて』(参月庵)という日本語によるすぐれた句集を出しておられます。 リンズィーさんと同じく30代で、ヴェルレーヌに心酔した後に、日本に留学したとき俳句の一茶に出会ったそうです。 ヴェルレーヌと一茶を統合したような作品世界を、大変うまい、音の内容のいい日本語で書いていらっしゃる。 汐引いてしばらく砂に春の月 鳥は死ぬまで同じ歌春のくれ 紫煙にも紫煙の影や春燈(はるあかり) この三つからもすぐ感じとれるように、一茶の世界がそのまま移って来たようで、日本とヨーロッパの叙情、ヴェルレーヌ的叙情と一茶的叙情を合わせて、この方自身の独特のものとしたような、極めてやわらかい叙情がある。 硬質な叙情のリンズィーさんとは対照的な位置にある。 |
||
◇日本語の方がいい作品ができる |
|
| 宗 |
お二人とも、芭蕉以来の日本の俳句の中軸をちゃんと押さえながら、ヨーロッパ詩の精神の中軸をもつかんでいる。 東と西の俳句と詩を合体して、今までのものを乗り越えている。 ことに世紀以降の、アメリカも含むヨーロッパの現代詩のレベルをも超えているんです。 そしてそれが日本語で行われているところに、大変な驚きを覚えるんです。 |
| リンズィー | でも、これは日本語だからこそできることだと思うんです。 |
復活させたい産業革命以前の英語の語彙[ごい] |
|
| リンズィー |
英語では、三行詩に結局とどまったんですが、過去には一行詩で書いてみたりとか、いろいろあったんです。 日本語と同じように英語でも五七五では情報量が多過ぎるから、今はもっと短く書いていて、短い一行、長い一行、短い一行というふうに、ある意味での定型を持とうとしているわけです。 定型があったほうが緊張感があり、おもしろいと思うんですが、それが英語ではやりにくいんです。 もう一つは、外国ではまだ余り歴史がないので、ほかの俳句を踏まえることがむずかしいんです。 読者が俳句をたしなむ程度のビギナーですので、ある俳句を踏まえても、気づいてくれなかったりしますが、日本語でつくればそういうこともない。 昔、産業革命が起こる前は英語にもすぐれた語彙がたくさんあったんです。 「ひこばえ」などと同じような、細かい自然を見るような言葉があったんですが、今は死語で、ないんです。 俳句で使おうとすると、「どういう意味?」、「誰も使わないよ」、そんな反応ばかり戻ってくる。 それを復活させようとしているんですが、イギリスとか、オーストラリアはまだいいんですけれど、アメリカのほうでは余り関心がなくて、それがむずかしい。 言語の可塑性とか、まだ日本では余りやられていない冒険をするにも、日本語のほうが、英語で書くよりもいい作品ができると思って、日本語でずっと続けているんです。 |
| 宗 |
日本語のほうが冒険ができるんですか。 それは、それだけ日本語に練達なさっているからですね。 |
『歳時記』を本のように読んで語彙を豊富に |
|
| 藤田 |
リンズィーさんは、我々日本人よりも日本語の語彙が非常に豊富でいらっしゃる。 もう使われなくなったような言葉もかなり修得されていますけれど、これは俳句を読んで勉強されたんですか。 |
| リンズィー |
「歳時記」を本みたいに読んでいるのと、わからない漢字があると、すぐ電子辞書で調べて、出てないときは漢和辞典で探して、鉛筆で全部書き込んでいるんです。 そうやって勉強しました。 自分がわからないものがあったら、どうしても知りたい。 生物学でもそうなんですが、これはわからないけどまあいいやで、さらさらと次に行くのは嫌いなんです。 『むつごろう』ではいろんな俳句を出しましたが、自分はここまでの俳句ができるけれど、余り冒険すると、「この人は全然わかっていないんじゃないか」というふうにもなるかなと思うんです。 基本はもうわかっていて、その上でいろいろやっていると理解されるように、これからがほんとの勝負かなと思っているんです。 |
| 宗 |
今までもほんとの勝負だったでしょう。 もはやほんとの勝負の中の何合目かにいらしていると思いますよ。 |
| 藤田 |
リンズィーさんはインターネットのホームページで日本語と、それを発音したローマ字表記と英訳とで俳句を紹介されていますね。 |
| リンズィー |
私はまず日本語でつくるというスタンスなんです。 ですから英語の句は日本語からの翻訳で、英語だけでつくった俳句はほとんどないんです。 「機の窓に静脈のあと氷河見ゆ」を英訳したのが on the plane window 三行詩のスタイルです。 |
|
◇外国では、どう受け止められたか |
|
| 宗 |
この座談会に出るために読んだ本の中から2冊、ご紹介したいんです。 佐藤和夫さんの『俳句からHAIKUへ &ト英における俳句の受容』と、星野慎一さんの『俳句の国際性≠ネぜ俳句は世界的に愛されるようになったのか』です。 ・ 佐藤さんは英文学を専攻された早稲田大学教授で、俳人でもあると思います。 星野さんは俳句もつくられるようですけどリルケやヘルマン・ヘッセ、19世紀末から20世紀にかけてのドイツ現代詩の翻訳や紹介をなさったドイツ文学者で、詩人でもある。 そういう立場で、ヨーロッパやアメリカで俳句を勉強した学者や実作者の作品から、ヨーロッパ人が俳句をどう受容しているかを紹介し、批判しているんです。 ヨーロッパの、現代詩に到る古来の詩の精神がどういうものかを語りながら、そういう詩の伝統で養われたヨーロッパ人やアメリカ人が、俳句をどういうふうに受けとめたかを語っている。 ヨーロッパ人の目を通して俳句を再批判した意味で、大変すぐれた俳句美学の本なんです。 |
| リンズィー |
外国でも俳句はどういうものか、わかっている人はちゃんとわかっています。 ただ、自分の言語ではそこまでつくれないだけなんです。 もちろんビギナーも多いですけど、わかっている人はわかっているんですよ。 その人たちがどんな作品をつくって、どう思っているのか、どういう受けとめ方をしているのかを、日本の中でもう一回俳句を考え直してはどうかと思っているんです。 |
近寄りやすく見えて実は開かれていない俳句という世界 |
|
| 宗 |
今のお話の外国の人たちの俳句のわかり方は、割合程度が高いと思うんですが、一般の人はどうか、フランスの評論家のロラン・バルトの作品『表徴の帝国』の中にこんなことが書いてあります。 「俳句は羨望をおこさせる。 その簡潔さが完璧さの保証となり、その単純さが深遠さの確認となるような(簡明さこそが芸術の証明だとする古典派的神話、即興にこそ第一の真理があるとするロマン派的神話、この二つの神話のせいで、こういうことになるのだが)さまざまな《印象》を、鉛筆を手にしてそこかしこで書きとめながら生のただなかを散歩したいと夢みなかった西洋の読者がなん人いるであろうか。 俳句は、近寄りやすい世界である。 そのくせ、じつはなにごとも語ろうとはしない。 こういう二重の性格をもつために俳句は、あなたの偏執、あなたの価値観、あなたの記号体系ぐるみ、もろともにあなたをおおらかに迎えいれてくれる礼儀正しい一家の主人のように、たくさんおもてなしをいたしましょうというように、意味に向って開かれているようにみえる。」 ところが開かれていないと次に言うんですが、これが一般のヨーロッパの、あるいは日本の人たちの俳句の受け止め方じゃないでしょうか。 |
| リンズィー |
そうだと思いますね。 |
| つづく |