| ■『有鄰』最新号 | ■『有鄰』バックナンバーインデックス |
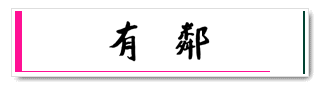
| 平成14年11月10日 第420号 P3 |
|
|
|
| 目次 | |
| P1 P2 P3 | ○座談会 小田原合戦 (1) (2) (3) |
| P4 | ○非運と豊潤の文学—樋口一葉 松本徹 |
| P5 | ○人と作品 吉住侑子と『旅にしあれば』 藤田昌司 |
|
|
|
| 座談会 小田原合戦 (3)
|
数奇な運命をたどって生き残った宣戦布告状 |
|||||||||
| 永原 |
北条の子孫といわれる北條龍彦さんは二、三年前に亡くなられましたが、彼はご自分のうちにあって、今も岡山県の預け先にある宣戦布告状の文書が秀吉が氏直に送ったものだと確信しておいででした。写しは上杉、毛利、伊達とかの大名に送っていますから、七つ、八つ同文のものでわかっているのがあるんです。その中で龍彦さんは、秀吉の出した文書で五人の右筆(ゆうひつ)を調べていき、筆跡を全部つき合わせた。すると、右筆楠正虎の手だということが分かった。
ただ、そこから先、どうしてこの資料が岡山県に残ったかということを言わなくてはならないのですが、これは難しい。それ以上は龍彦さんの推理になるわけですが、私は推理は当たっていると思う。
北条は小田原が落城したときに、氏直が助命されて三百人ぐらい連れて高野山に行ったといいますから、一定の物を持っていったと考えてもおかしくない。だけど氏直は天正十九年、負けた翌年に疱瘡になって死ぬ。そうすると、氏直のおじさんに当たる氏規の流れに、秀吉は北条の名跡を残してやろうと一万石やって、河内狭山(大阪府大阪狭山市)の大名にした。 ですから、恐らく小田原本城から持ち出されてきたものが、何らかの形で北条の本領の備中(岡山県)に移った。そこまで龍彦さんは調べた。秀吉が北条に出した宣戦布告状は数奇な運命をたどって、本物は生き残ってきていると思います。 |
||||||||
| |
|||||||||
| 岩崎 |
最後に秀吉と対決していくときどんなに秀吉が来ても、大外郭に囲まれた小田原は落ちないぞという自信はなかったんですかね。
|
||||||||
| 永原 |
こういうふうに考えたらしいんです。天正十八年いっぱいを頑張り抜けば、必ず秀吉側では兵糧不足問題とか起こると。大軍を集めて長陣の包囲なんかしていると、やることがなくて、みんな女房を呼んだり、商人が物を売り込みに来たりで内部崩壊が起こると見ていたと思う。だから、何も永遠に守り抜かなくて、今年いっぱいだと。
|
||||||||
| 岩崎 |
要するに長期戦に持ち込めば勝てると。それと氏政には、永禄四年と十二年の二回、上杉謙信と武田信玄が小田原城の城下まで攻めてきたとき、町は焼かれますが、最後まで守りぬいたという自信もあったでしょう。
|
||||||||
| 篠崎 |
北条の支城は関東に幾つあったんですか。
|
||||||||
| 山口 |
俗に百とか言われていますが、正確には把握されていませんね。
|
||||||||
| 永原 | 毛利が「関東八州諸城覚書」に書いている。玉縄[(たまなわ)鎌倉市]、三浦、下田、河越、鉢形(埼玉県寄居町)、八王子、岩付(埼玉県岩槻市)とか、百に近い数ですね。北条領国の本城は小田原でその主な支城には、一族、重臣が入って一定の抵抗力を持っている。そして小田原は大外郭という総まわり九キロぐらいのお城のお堀、大土塁をつくって、町ごとぐるりと囲むわけです。
だから、町人もすべてその中に入ってしまう。関東地方全体から呼び寄せた家来、それから背反をおさえるための証人(人質)も全部抱え込んでしまう。兵糧もすべて持ち込みで、自分の分を確保してなお余りがあったら小田原に全部売れと。ですから氏政、氏直のほうは兵糧も人も可能な限り、これは侍だけじゃない形で、小田原という、いわば運命共同体の世界をつくってしまったわけです。 |
||||||||
けた違いの秀吉の資金力 |
|||||||||
| 篠崎 |
北条氏にもかなりの財力があったんでしょうね。
|
||||||||
| 永原 |
だけど、それは秀吉に比べたら……。
|
||||||||
| 篠崎 |
けたが違いますか。
|
||||||||
| 永原 |
秀吉のほうは、史料がありますが、兵糧買い付けなどにあてただけで黄金一万枚。黄金一枚というのは純金に近い九十何%で、四十四匁ぐらいです。一枚で十両、それを一万枚使っている。
そのほかに奉行が管理していた二十万石の米があった。秀吉のほうは遠くから来るわけでしょう。二十万人以上の軍隊がいて、伊勢・淡路島・伊予のほうから秀吉の家来になっている加藤嘉明、九鬼嘉隆の水軍も来るわけです。
秀吉の小田原の本城は一夜城と言いますが、最近の発掘で見たら、一夜どころか、石垣は本格的なもので、ごまかしに、ちょっと城らしくしたなんていうものではない。本物の城です。後に、朝鮮出兵をやるときも、名護屋でも、みんな本格的な城をつくている。 出先でもそれをやることが秀吉の特徴ですが、それをやるお金ですね。 幾ら大軍と言っても築城の人夫が要るでしょう。北条は地元だから、自分の領国から小田原城強化のために人夫をたくさん集めてやったわけですが、秀吉は金でやるしかないわけです。地元の人たちは金をもらえば秀吉方の仕事でもやるでしょう。それでやったわけです。 このお金を考えると北条とはけた違いの財力です。秀吉がそれまでの大名とどこが違うかというと、金(きん)をいかにたくさん備蓄したかということです。「きん」は秀吉自筆文書で「きがね」といっています。時々、金配りといって、お花見をやって大名たちに配ったり、公家にやったりするわけですが、それはものすごいです。秀吉は、金の有効性を一番知っていて、大量に持っていた。 上杉謙信は死んだときの財産調べで二千数百枚しかなかったけど、秀吉は今度の戦争だけで一万枚です。関東でも金はたくさん出たらしいけれども、秀吉のところに集中するメカニズムは、どういうものか解かなければならない。 |
||||||||
| 山口 |
結局、小田原城の包囲が徹底される一方で、講和の動きが出てくる。最終的には、氏直が秀吉に投降して、五か月に及ぶ合戦の幕を閉じることになります。
|
||||||||
| 篠崎 |
北条氏の文化ということでは。
|
||||||||
| 岩崎 |
例えば、足利将軍家が収集した南宋の画僧玉澗(ぎょくかん)が描いた「遠浦帰帆(えんぽきはん)図」などの東山御物中というものや、鎌倉の建長寺、円覚寺にあった仏画類が早雲寺や本城にはかなりあった。それを秀吉はみんな召し上げて京都に持っていき、大徳寺に寄付したり家康に与えたりしている。 北条氏の収集絵画はかなりレベルの高いもので、雪村周継(せっそんしゅうけい)という室町期の、雪舟に次ぐ最大の画家が会津からわざわざ見に来た。それで、いろいろな刺激を受けながら、室町のトップの絵師になっていくという経過もある。かなり重要な絵画類なんですね。 現在でも国の重文になっている「五百羅漢図」とか、臨済宗の「三祖師画像」は全部京都の大徳寺にありますが、それは全部早雲寺から持っていったことは確かです。 それから中には、秀吉が千利休に与えたのを、利休自身が、こんな大切なものをもらってもというので、大徳寺に寄付したものもある。 |
||||||||
| 永原 |
早雲寺にあったものと、本城にあったものと両方考えなければなりませんが、北条の歴代当主たちが、山科家などの京都の公家たちに、宗長のような連歌師を通して例えば『源氏物語絵巻』の写しをつくってもらうとか、あるいは、自分の持っている物に奥書を書いてもらうとか、そういう形で文化的な交流をやっていて、その都度、金十枚などという形であげるんです。鑑定ですね。
これは大変なことなんですね。そうすると、公家のほうは大喜びで、「手舞い、足地につかず」とか史料に書いてある。 |
||||||||
今川氏経由でも京文化を取り入れる |
|||||||||
| 岩崎 |
北条のコレクションのうち、いわゆる京文化、中央文化を小田原の地に持ってくるルートとして、一つは、初代早雲自身は、申次衆という室町幕府のかなり重要なところにいた。それで、幕府に出入りする公家は、特に外郎(ういろう)などと接触があったと思います。それでいち早く外郎を小田原に呼んで、その外郎が文化のお使い人として、例えば二代氏綱が「酒伝童子絵巻」を狩野元信に注文して描かせ、それができ上がるまでは外郎が全部使いに出ているんです。
|
||||||||
| 永原 |
京都の文化の高さを北条はよく知っていて、氏綱は鶴岡八幡宮の大造営を生涯の事業としてやりましたが、興福寺が抱えていた京都と奈良の番匠、瓦職人等々、建築に必要な人を呼ぶ。歴代、そういう京都の文化を取り入れた。
|
||||||||
| 岩崎 |
一つは、駿河の今川経由で来ているものもあります。例えば連歌師の宗長、刀鍛冶の島田義助とか。冷泉為和なんかも今川の居候で逗留していて、それで小田原へ。」 |
||||||||
| 永原 |
今川の所へは、公家がたびたび来ている。
|
||||||||
| 岩崎 |
そうなんです。それが小田原に歌の指導なんかに来ていますね。
|
||||||||
| 永原 |
だから、今川は公家風で、北条は早雲以来武辺だというのは間違っていると思う。大名は戦争屋だけではなくて、地方国家の君主ですから、文化というものは支配のための一要素として絶対欠かせないんです。つまり領内のさまざまな階層に対して秀でた地位というのは、いかに文化を目に見える形で持っているかということなんです。
|
||||||||
山上宗二が「小田原天命」の誕生に関わる |
|||||||||
| 岩崎 |
小田原の場合、天正十八年で北条文化は完全に崩壊してしまうんですが、それ以前に初代早雲、二代氏綱から始まって、五代氏直まで、中央文化の導入があって、いろいろな人びとがやって来たので、それなりの文化ができ上がってくるわけです。
小田原の場合は鎌倉文化との接点があったから、鎌倉の水墨画系の画人や会津の雪村も来る。一方、京都から狩野玉楽や番匠も来る。西の中央文化と東国文化が接触する場が小田原だと思うんです。 後世、小田原物とよばれている小田原狩野の絵画とか、「小田原天命(てんみょう)」とよばれる茶湯の釜が生まれてきたと思うんです。室町時代から関東のよい釜は天命と呼ばれ、小田原天命は河内狭山から来住したといわれる鋳物師山田二郎左衛門によって鋳られたものです。 小田原天命ができたのは、千利休の弟子で茶道者の山上宗二が小田原に来遊していたこととも深くかかわっていたといわれてます。宗二は小田原合戦中、早雲寺の茶会で秀吉の怒りをかって自害させられてしまいます。 |
||||||||
『吾妻鏡』の有力な写本も北条氏が所有 |
|||||||||
| 岩崎 |
北条氏のコレクションは、天正十八年の小田原攻めで一挙になくなった。だから加賀みたいに近世社会の中に残らなかったわけです。
|
||||||||
| 篠崎 |
中世の『吾妻鏡』を三代氏康が読んだと。金沢文庫にあったんでしょうね。
|
||||||||
| 永原 |
『吾妻鏡』の有力な写本の一つは小田原にあった。それが家康の手に入った。だから、城が全部燃えてしまったのではなく、氏政が出てきて腹を切ったから文化財は残った。城にあったいいものは秀吉も手に入れたけれども、大部分は家康の文庫にしたわけです。
|
||||||||
| 岩崎 |
二代氏綱の弟、北条幻庵などは結構いろんな古典籍を残している。
|
||||||||
| 篠崎 |
小田原の町自体はどうなったんですか。
|
||||||||
| 永原 |
家康は小田原城を落とすと、すぐに秀吉から江戸に行けと言われる。そのとき江戸は、小田原に比べたらまだ漠たるもので、家康に商人がついていったかどうかわからないんです。
外郎は小田原にそのままいるわけです。冨山という伊勢から来た有力商人は、城が落ちたときに小田原を離れて練馬に移り、江戸でまた大きな商人になった。伊勢商人の一番の舞台は小田原です。 |
||||||||
| |
|||||||||
| 篠崎 |
合戦が終わって、氏直は高野山に追放され謹慎することになりますね。
|
||||||||
| 山口 |
八月に高野山に着きますが、翌年の二月には家康を通じて赦免の意が伝えられます。家康の縁者ですから。そして、八月に大坂城に入り、正式に赦免になる。このとき一万石の知行を与えられたようですね。
|
||||||||
| 永原 |
それを、氏直とともに切腹をさせられずにすんだ氏規が継承する。
|
||||||||
| 山口 |
実際には氏規の子供の氏盛が継承しました。秀吉に旗本として取り立てられたのは氏直と氏規なんですが、氏直はすぐ亡くなるので、その名跡は氏盛に継承され、遺領は氏規とその子供の氏盛に与えられます。氏規に与えられた分も、最終的には氏規が死んだ段階で、氏盛に継承されたと見てよいでしょう。それからずっと幕末まで続くんです。
|
||||||||
北条氏の家臣たちは登用されずに土着 |
|||||||||
| 篠崎 |
北条氏が近世に与えた影響は何かありますか。
|
||||||||
| 山口 |
家康が、北条氏の政策をかなり継承している。
|
||||||||
| 岩崎 |
江戸幕府の東海道の伝馬制度は引き継がれていったと言われています。
|
||||||||
| 永原 |
地方にいた北条の家臣たちは意外に登用されず、土着したのではないかと思います。これほど北条の発給文書が村々の旧家に残っているのはほかに例がない。小代官とか名主といった村の一番中心になる主だった家の人は北条の下級の家臣で、大体三十貫文以下だけれど、侍にみんな編成させていた。だけど、家康は彼らを登用しなかったから、百姓になって村の旧家として文書を持っている。
|
||||||||
| 山口 |
小田原方面の例を見ると、名主とか組頭とか江戸時代に村役人をつとめた旧家の最も古い文書は秀吉の禁制である場合が多いんです。北条時代の古文書を伝えている旧家はありますが、北条時代に小代官とかをやっていたこれらの旧家の文書は、そこで切れていて、秀吉の禁制以降の文書がない家も多い。こういう面からも、戦国末から近世初頭にかけて、村の指導者の系統にある程度の断絶があるのではないかと思います。
|
||||||||
| 篠崎 |
きょうは本当にありがとうございました。
|
||||||||
| ながはら けいじ |
| 一九二二年中国大連市生まれ。 |
| 著書『戦国期の政治経済構造』岩波書店7,350円(5%税込) ほか。 |
| いわさき そうじゅん |
| 一九三三年箱根町生まれ。 |
| 著書『浮世絵が語る小田原』夢工房2,100円(5%税込) ほか。 |
| やまぐち ひろし |
| 一九五九年秦野市生まれ。 |
| 共著『小田原市史通史編 原始 古代 中世』6,300円(5%税込)。 |
|