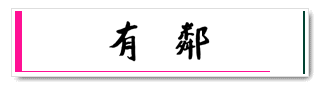緊張感いっぱいの天敵同士オオカミとヤギの友情
|
| 藤田 |
どうしてそれだけ熱狂的な感動を呼んだんでしょう。井辻さんのお立場からは、どう思われますか。
|
| 井辻 |
佐野洋子さんの『100万回生きたねこ』ってありますね。100万回死んで、100万回生きたねこの話。そのねこは100万人の飼い主がみんな嫌いで、一回も泣かなかった。そして、のらねことして生まれたときに白いねこを好きになり、その白いねこが死んではじめて泣き、死んでしまったという話ですが、『あらし』を読んだときに匹敵する衝撃だったんです。
どこが似ているのか。『100万回』は、輪廻転生という、乗り越えられない掟を使っていますよね。『あらし』も、ものすごくせっぱ詰まった状況の中で、必死に自分を抑える。会話も命がけのぎりぎり。ヤギはヤギで一生懸命だし、オオカミはすごく切実に食べたい。でもだめだという、何か業のようなものをしょっている感じがいいのかもしれないですね。それを二人が相手を思う愛で乗り越えるみたいなところに、むしろ、大人が感動する。オオカミとヤギのキャラクターと、その会話がいいんですね。オオカミの「〜でやんす」という。
|
| 藤田 |
どうしてオオカミとヤギにされたのですか。
|
| 井辻 |
ほかの絵本にもあるし、オオカミがお好きなんですね。
|
| 木村 |
基本的に言うと、オオカミが好きなんです。
|
| |
主人公同士が真実を知らない緊迫感
|
| 木村 |
講演で、ヤギの気持ちになって読んだか、オオカミの気持ちだったのか、その二匹を物陰から見ている者の気持ちか、手を挙げてもらうと同じぐらいいるんです。
普通は、すべて物語には主人公がいて、主人公に感情移入するものなんですね。
|
| 井辻 |
普通は、誰か一人の人物に焦点が絞られる。
|
| 木村 |
ところが、これはヤギになるか、オオカミになるか難しい。主人公同士が真実を知らないんですよ。
|
| 井辻 |
離れたところからそれを見ている。
|
| 木村 |
こっちから見ている読者しか知らないという構造がおもしろいので、それでやろうかなと。
それとお互いが天敵であることを知らないというのが浮かんだんです。オオカミが好きだからすぐにオオカミ。でも、天敵は、ぼんやりとでも見えたときにウサギじゃ小さいし、ブタじゃ丸い。ヤギだったら、大きさ的にも形も近いかな、と。ヒツジだと体を寄せ合ったら毛むくじゃらだし(笑)。それだけの理由でこの二匹がでてきたんです。
|
| 井辻 |
すごく緊迫感がありますね。会話が刃の上に立ってる見たいな。
|
| 木村 |
もうばれるんじゃないか、ばれるんじゃないかという緊張感がすごくある。
もう一つは、悪役はいないということなんです。ドキドキハラハラするのはほとんど悪役がいるんです。だけど、これは立場が違うだけなんです。食物連鎖の中で、この二匹は草食動物と肉食動物と、単に立場が違うだけで、悪くはないわけです。そこが書きたかったんです。悪いやつを出せば楽なんです。
|
| 井辻 |
グリムなどはオオカミは必ず悪いということになっていて、現実に、牧畜をやっている人がそう感じることはあるにせよ、オオカミは悪の象徴動物になっていますね。そのオオカミものでも、木村さんの本は、本当に動物そのものを見つめているところが新しいですね。
|
| |
オス同士だけれど描いているのはオスとメスの関係
|
| 井辻 |
ガブとメイは異性なんですか。ちょっとわからない。恋愛ものとして読んでいる方もいるみたいですね。
|
| 木村 |
メイはオスだと思いますか、メスだと思いますかというのも、手を挙げてもらうと半々なんです。
|
| 井辻 |
私はオスだと思っていたので、どうしてこれ恋愛ものなんだろうと。丁寧だけど、何かしゃべり方に芯があって、オスっぽいなと思ったんです。
|
| 木村 |
オス同士なんですけど、オスとメスの関係を書いているんです。食欲と同じ本能ですから、ある意味でここのやりとりがすごく近くなる。食べたい物を我慢しながら、いろいろしてみたりするところがちょっと近いので、そういうものも計算しているんですけれども、でも、ヤギをメスにすると、何だ、恋愛ものを動物にしただけかとなっちゃうんですよ。
|
| 井辻 |
露骨になる。
|
| 木村 |
オスにすることによって、見方がたくさん出てくると思って、あえてオスにしたんです。にもかかわらず、どっちとも書かなかったんです。イタリア語版でも、女性名詞・男性名詞があるから、どちらにもならないように翻訳してもらった。
それから、聞いただけで、どちらが話しているのか、わかるように「〜でやんす」とか「なんとかっすね」とか、オオカミのイメージに合わせた言葉をつくったんです。
|
| 井辻 |
ちょっとやさぐれた感じというか、それが格好いい。
|
| 井辻 |
ちょっと変な小説として入ってきたのを学生たちが、自分たちの新しい文学ジャンルを見つけたと思った。
世界を支配する野望に燃えて戦争を始める冥王サウロンにベトナム侵略している米国や、あるいは指輪に核兵器を見たり、のどかに暮らしているホビットはヒッピーやフラワーチルドレンとか。若者たちのカルト的作品だった。それに加えて、アメリカ人は神話とか伝承とかを持っていないので、実はすごく好きで飢えているんですよね。
|
| |
自由な発想とキャラクターのアメリカ、世界観に凝るイギリス
|
| 井辻 |
アメリカオリジナルのファンタジーは、1900年にF・ボームが書いた『オズの魔法使い』シリーズ( 書籍リスト)ですが、これはほとんどメカニカルな、機械仕掛けみたいなファンタジーランドです。それまではみんなイギリスなどからの借り物だったんです。 書籍リスト)ですが、これはほとんどメカニカルな、機械仕掛けみたいなファンタジーランドです。それまではみんなイギリスなどからの借り物だったんです。
で、トールキンが憧れのイギリスの伝承を持ってきたので、すごく喜んだと思うんです。しかも、作者が第二世界をつくっていいんだということにしたので、アメリカ人は自分たちにはないけど、つくればいいんだと思って、それで一気に亜流の異世界ファンタジーが出たわけです。
アメリカだとアドベンチャー志向が強いのですが、例えばル=グウィンの『ゲド戦記』( 書籍リスト)は魔法や魔法使いを主題にして地道に世界の構造を問いかけた作品をつくった。 書籍リスト)は魔法や魔法使いを主題にして地道に世界の構造を問いかけた作品をつくった。
アメリカは伝承を持っていないだけに、いろいろ気楽につくるし、実験作もやる。あと、おもしろければいいじゃないかが徹底しているので、テンポが速い。
イギリスはトールキンだけでなく、伝統的に世界設定や背景にうるさい。アメリカでは、たとえば同じケルトを下敷きにしていても、キャラクターでしっかり引っ張る。世界設定もしているんですけれども、すごくわかりやすいアドベンチャー・ファンタジーになっている。それでも『指輪物語』は世界造りの原点というか、バイブルとしてずうっとあるみたいですね。
|
| |
エピック・ファンタジーの原点として紹介された『指輪物語』
|
| 藤田 |
『指輪物語』は読者の範囲が広いですね。
|
| 井辻 |
カルト的だった時代は、読者は一部だけれど、もっと熱狂的だった。今は、ファンタジーが結構認知されてしまったので、割といろんな人が読んでいますね。
|
| 藤田 |
今のファンタジーブームの原点と言っていいんでしょうね。
|
| 井辻 |
そうですね。あれだけの長さと密度と強度で世界をつくったのはすばらしい。そういう感じで見られているところがあるんじゃないでしょうか。
|
| 藤田 |
どのくらいの国で翻訳されているんですか。
|
| 井辻 |
80何か国かな。百まではいっていないかもしれない。日本で翻訳が出たのは73年ぐらいで、最初は荒俣宏さんがエピック・ファンタジーの原点と紹介した。それでSF系のオタクの人たちが飛びついたんです。
そのあと2〜30年、一回、エンデの『はてしない物語』( 書籍リスト)のブレークがありましたが、『ハリー・ポッター』が出るまでは『指輪物語』がバイブル。で、世界設定に凝るファンタジーが続いていたところへ『ハリー・ポッター』でキャラクター優位が復活した。そしてトールキンも原点として読み返されるようになった。 書籍リスト)のブレークがありましたが、『ハリー・ポッター』が出るまでは『指輪物語』がバイブル。で、世界設定に凝るファンタジーが続いていたところへ『ハリー・ポッター』でキャラクター優位が復活した。そしてトールキンも原点として読み返されるようになった。
|
| |
架空のなかにも日常との接点を常に意識して創作
|
| 木村 |
そういうふうなファンタジーが、一過性ではなく長く読まれるというのはどういうところなんでしょうね。
|
| 井辻 |
風俗などとは関係ないから、時代によって古くならないというのが一つあるんです。当時の風俗や社会の倫理とかを知らないとわからない話だと、その時だけは売れるんですけど、ファンタジーはそうではないわけです。
|
| 木村 |
物語の世界が抽象的だからこそ、逆に古くならない。そういう意味で、長く続くのかな。
|
| 藤田 |
それに、子供は大きくなって、どんどん読者が新しくなりますからね。
|
| 木村 |
僕もそう思っていたんです。でも、『100万回生きたねこ』の読者はほとんど大人なんです。いまだにベストテンに入っている。本質的というのかな、古くならない要素というのがあるからなんでしょうかね。
|
| 井辻 |
それが非常に普遍的なものを射抜いていればずっともつんです。
|
| 木村 |
僕は、ファンタジーが全く架空というより、話に身近な日常の部分との接点がないとおもしろくないと思っているんです。全部架空になると、それはいろんな意味での接点がなくなり、何か勝手にやればみたいな感じになっちゃうから、常に日常とのつながりというのを意識する。
『あらしのよるに』は日常とはもちろんつながらないんですが、架空なんだけど、この二人の中のあるところに日常を感じるものを常に入れようとすることを、僕は原点に考えているんです。
|
| 井辻 |
オオカミの鼻が詰まっていたから、においがわからなかったとか、すごくリアルですね。ファンタジーこそ世界の手ざわりは必要。
|
| |
普通の暮らしから異世界に行くパターンが多いファンタジー
|
| 藤田 |
ファンタジーのツールというのは、そういうことも考えられるわけですか。
|