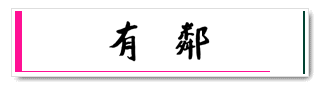| 木村 |
生き返ったのがみんな同じ動物とは限らない。人によって、みんな違って生き返る。
|
| 井辻 |
全然、作者の思惑を超えてということですね。
|
| 木村 |
いろんなお便りを見ていると、100人が100人全部違うんです。ファンタジーの架空の世界のすべてを、自分の頭の中でもう一回つくっているんですね。だから、皆さんからの生々しいお便りが来たときに僕は不思議な感じがするんです。
|
| 藤田 |
読者の喜びというのは、まさにそこにあると思いますね。
|
| 木村 |
読者が一人一人演出家になって、心の中でその世界を映像化して創っている。記号の羅列を生き返らせてるんだ。だから読書はクリエイティブなことなんです。
|
| |
絵は動物園の飼育係だったあべ弘士さんに
|
| 藤田 |
お書きになるときはイメージとして絵を想定されたんですか。木村さんは絵がご専門ですよね。
|
| 木村 |
そうです。だから、絵は浮かぶんです。
|
| 藤田 |
絵本作家で好きな作家はいらっしゃいますか。
|
| 木村 |
田島征三さん( 書籍リスト)なんか好きですね。最初のころはそういう絵本をつくりたいなと思ったんです。でも途中からそういう人と組めばいいや、というふうに変わった。(笑) 書籍リスト)なんか好きですね。最初のころはそういう絵本をつくりたいなと思ったんです。でも途中からそういう人と組めばいいや、というふうに変わった。(笑)
『あらしのよるに』を書いたときには、あっ、俺が絵描きとして描きたかった絵はこの話なんだと思ったんです。こういうのに絵をつけるのが望みだったので、ほんとのことを言うと、どっちにしようかなって随分悩んだんです。
でも、欲張らないで、今回は文章だけでいこうと思ったんです。最終的に、あべ弘士さんに頼んでよかったと思っています。
|
| 藤田 |
文章と絵のイメージとが、ぴったり合っていますね。
|
| 木村 |
その当時は、あべさんは旭川市の旭山動物園の飼育係でしたが、すぐに仕事を引き受けてくれなかった。でも、原稿を読んだら、すぐにイメージが浮かんだらしいんです。それですぐやることになったのですが、でもなぜか毎回、絵が全部違うんです。
|
| 井辻 |
それが気にならないというのは不思議ですね。
|
| 木村 |
みんなちゃんとガブとメイに見えるところが、この人のすごさなんですね。だから、そこの違いがまたよくて、違うから余計みんな頭の中に勝手につくり上げた世界にしやすいのかな。
|
| 井辻 |
でも、この二匹の声は、すごくよく聞こえてきますもの。
|
| 木村 |
この不親切さがいいのかな。
|
世界のあり方を探求していく『ゲド』戦記
|
| 藤田 |
そのほかには?
|
| 井辻 |
「外へ抜けでる」。つまり心理や日常ベッタリから抜け出し、外からとらえ直す。このへんはエンデも言っているんですけど、自分の内面を見ようと思っても、余りはっきりわからないけど、外の世界はそれを反映しているので、外の世界にそれを見ていく。
ファンタジーは、別世界とそこで起こるドラマを描くんですけど、それが何か内面のドラマ、象徴的できごとであるというふうになっている。
|
| 藤田 |
荒唐無稽ではファンタジーにならないということですね。
|
| 井辻 |
設定は荒唐無稽でもいいのですが、いったん現実設定をとっぱらったところに真の成長とか愛とか、世界とは何か、とかの本質を描くわけです。
|
ファンタジーは不確実な時代の中で確実なもの
|
| 藤田 |
『あらしのよるに』は内面のリアリティーという面では、今の子供たちにぴったりくるものがあるんじゃないかと思いますね。
つまり、今の子供たちは非常に孤独で、一人ぼっちになっているから、全く相性が悪いと思われているオオカミとヤギの間ですら友情が成立すると言われると、そうかということで、感動するのではないかと思いますね。
|
| 木村 |
確かに周りを見渡すとお父さんとお母さんが、いつまで一緒にいるかわからないとか。でも、大人でも別の意味での不信時代で、銀行に預けておいたお金が返ってこないかもしれない。スーパーの表示もうそかもしれない。
|
| 井辻 |
頼れると思っていたものがそうじゃなくなってきた。
|
| 木村 |
そうですね。大会社に勤めていても、リストラとか倒産とか、ニューヨークのツインタワービルがまさに一瞬にして崩れるとか、今までの信じるもの、周りを取り囲んでいるものが全部崩れてきた。信じられる、頼りになるものを探すと何でしょうねというぐらいで。
|
| 井辻 |
現実がすごく確固としていて、安全で、ここにいて、ここでちゃんとやれば大丈夫という時代でなくなってしまった。
|
| |
最も信じないもの同士が信じあう努力をする
|
| 木村 |
オオカミとヤギは天敵で、地球上で最も信じないもの同士が、お互いを信じる努力をする話ですから、今の子供たちが、これを手がかりにして、何か求めている状況なんでしょうね。
|
| 井辻 |
でも、寓意とか象徴に流れるのでなく、二人の間に流れる、やばいんだけど、何か一緒にいたいみたいなリアリティーが、すごく切ない感じがする。
|
| 木村 |
そういえばそうですね。やばいんだけど、一緒にいたいというのが原点かなという気もしなくはない。
|
| 井辻 |
仲間に対しては裏切りですね。
|
| 木村 |
いけないことをちょっとすること。常に、やってはいけないことを守りながら社会生活をしている人は、そのきわどいところを求めているのかもしれないと思うことがあるんです。
何かやばいための緊張感、緊迫感というのがすごくて、そこでぎりぎりのところで言葉を発せられているといった場合の、そのすごい立ち上がり方というか。
|
| 藤田 |
非常に緊迫した関係の中から人間関係が生まれ、会話が生まれているということ、それが、読者に対してのアピールになっていると思いますね。
そんなところに、ファンタジーがブームになっている要素があるんでしょうかね。
|
| 井辻 |
木村さんが言われたように、時代というか、地球全体が安定したところじゃなくなっていって、環境も危ないし、政治体制も、経済も、そういうまさに不確実な時代の中でステイブル(確実)なものというと、実はフィクションの世界は逆に安定しているということもありますね。
|
| |
ファンタジーと現実の世界を近づけるテクノロジー
|
| 井辻 |
あと、テクノロジーの進化によって、現実と夢の世界の境を結構、消すことができたということじゃないでしょうか。
|
| 木村 |
テクノロジーの発達は、例えば、ここ20年ぐらいでものすごいじゃないですか。これってもしかすると、非常に魔法に近づいているような……。
|
| 井辻 |
インターネットでもしくみが全然わからないブラックボックスですものね。
|
| 木村 |
昔、ポットのことを魔法びんと言った。お湯が冷めないだけで魔法だったんですよね。それを考えたら、ボタン一つで違う世界が見れたり、今の現実は魔法だらけなわけです。
|
| 藤田 |
本当にそうですね。
|
| 木村 |
僕は子供のころは、うちにテレビがなかった。洗濯機もなかった時代が、ほんのわずかの間に魔法だらけになってきている。そういう意味で言うと、ファンタジーはどんどん近づいている。
|
| 井辻 |
魔法って完全にバリアフリーになっちゃいましたね。今、みんなが遠くの人と話しながら歩いているなんていうのは、魔法としか言いようがない。そういう意味では魔法だらけになってしまったこの現実の中で、魔法が改めて注目されているという感じがする。もうそれ自体が不思議じゃないですね。
|
| 木村 |
不思議にする必要はないぐらい、ちょっとの違いで魔法ができちゃう。
|
| 井辻 |
「アトム」に携帯電話みたいなのが出てきていたという話がありますね。そういうものが90何パーセント実現している。あのころは、SFとか、まさに夢の世界とか、あり得ないと思っていたことが。
|
| 木村 |
不信の停止をしなくても、かなり近いものがあるのかな。
|
| 井辻 |
そのままですね。かなり追いついちゃった。
|
| 木村 |
別世界をつくるというのは、あまり書いたことがないから、書いてみたいなという気にはなりましたね。
|
| 藤田 |
大変いいお話をありがとうございました。
|