Web版 有鄰 第430号 有鄰――かならず仲間がいるよ /高島俊男
有鄰――かならず仲間がいるよ – 特集1
高島俊男
有隣堂さんから原稿の御注文をいただいた。
有名な本屋さんですね。小生は兵庫県の住人だが、でも「横浜の有隣堂」と言えば知ってますもの。その上、数ならぬ小生の本をとりそろえていて、よく売ってくださるのだそうな。ありがたいことです。もう日ごろから、横浜のほうへは足をむけて寝られないと思っております、ハイ。
御注文といっしょに、情報紙『有鄰』をお送りくださった。
第1面の最上段中央に、武者小路実篤先生の風格ある字で、「有鄰」という題号がドンとすわってますね。その左右に説明がついている。
きょうは、この「有鄰」ということばについてお話をいたしましょう。――なお、この「有鄰」の鄰の字と、有隣堂の隣の字とは、ちょっとちがうけれど、おなじ字です。そのことはあとでゆっくり申しましょう。
題号右がわの説明にあるように、「有鄰」というのは『論語』に見えることばです。論語のなかでも有名な一節だ。
で、その本文はと言えば、「子曰徳不孤必有鄰」と、これで全部です。「子曰」(先生がこうおっしゃった)というきまり文句をのぞけば、たったの6字。短いほうではトップクラスです。意味は、「りっぱな心がけの人が一人ぽっちということはない、かならず仲間がいる」ということですね。
むかしから、学校や本屋さんなどの名には論語からとったものが多い。というのは、学校や書店はもちろん学問と関係が深い。そして論語は学問の総本山みたいに考えられていたからです。
また論語には、校名や店名にふさわしいことばが多い。たとえば冒頭の「学而時習之」。ここからとったのが「学習院」ですね。「時習館」という学校もある。
本屋さんで一番有名なのは三省堂でしょうね。「吾日三省吾身」(毎日毎日何度もわが身を反省する)からとったものだ。
なかでも「有鄰(隣)」というのは、学校や本屋さんの名にぴったりだ。たとえば本屋さんなら、「本を読んで勉強しようとする君、君は決して一人じゃないよ、ウチのお客さんには、君とおなじ志をもつ人たちがたくさんいます」とそういう意味になりますね。
 の意味は「おなじものがならんでいる」
の意味は「おなじものがならんでいる」
-
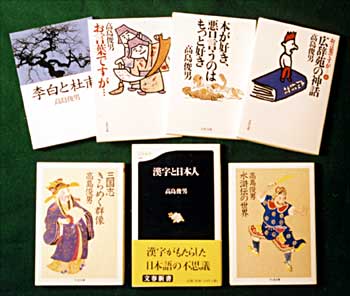
- 高島俊男氏・著書画像
この鄰(隣)の字には「![]() 」という部分があるが、この部分をもつことばは、本来みなおなじ意味です。それは「おなじものがならんでいる」という意味だ。
」という部分があるが、この部分をもつことばは、本来みなおなじ意味です。それは「おなじものがならんでいる」という意味だ。
それが一番わかりやすいのは「鱗」つまり魚のウロコですね。おなじようなのがズラッとならんでいる。そういうようすが「![]() 」。このばあいは魚だから、魚へんをつけてあるわけです。
」。このばあいは魚だから、魚へんをつけてあるわけです。
それから「燐」というのは人魂(火の玉とも言う)ですね。小生まだ人魂の実物を見たことがないのだが、あれは2つ3つ、あるいは4つ5つとつながって飛ぶものなんだそうです。色は青だそうだから、ガスコンロの火の大きいの、と思えばいいのでしょう。火だから火へんをつけて「燐」。
そういうわけで鄰・隣はおなじような家がならんでいることです。日本語で「となり」と言うと両側の2軒だけを指すみたいだが、無論そうじゃない。近くにある家はみな鄰・隣である。そういうことから意味がひろがって、家だけでなく、むかしの辞書が「近也、親也」(ちかいこと、したしいこと)と説明するように、一般に近い親しい関係にある人やものをも言うようになった。
論語の「必有鄰」の「鄰」はまさしくその意味ですね。家ではなく、「おなじ志をもつ仲間」つまり人を指している。
本紙題号の横にこの「鄰」を「村里の意」と書いてあるが、これはいけませんね。「鄰」は家がかたまってあることだから、集落の意にもちいることもあるが、しかしここは論語の「必有鄰」の説明なんですからね。「よい心がけの人が一人ぽっちということはありません。きっと村里がある」では意味をなさない。
どうしてこれまでだれも気がつかなかったのだろう。不思議ですね。
 の意味は「人があつまって住んでいるところ」
の意味は「人があつまって住んでいるところ」
鄰と隣とは同じ字だと上に申しあげた。元来は鄰であったようです。漢字の御本家中国では一貫して鄰のほうをもちいることが多いし、『廣韻』や『康熙字典』などむかしの権威ある字典でも「隣は俗字」としてあるので、題号の横の説明を書いたかたは鄰を「正字」となさったのでしょう。しかし日本では、従前から「隣」のほうがよくもちいられてきました。
この「![]() 」という字(というか、字の部分ですね)は、本来は、字の左がわにある
」という字(というか、字の部分ですね)は、本来は、字の左がわにある![]() と右がわにある
と右がわにある![]() とは別の字なのです。
とは別の字なのです。
右がわの![]() は、もとは「邑」の字で、これが簡略化されて「
は、もとは「邑」の字で、これが簡略化されて「![]() 」になった。「人があつまって住んでいるところ」の意です。都、郡、郷、邦などはごくわかりやすいですね。一見したところでは、どうしてこれが「人のあつまっているところ」なのかわからない字――郵とか郎とか邪とか――もありますが、これらも、一つ一つの字についてしらべてみると、もとはみな人があつまっているところ――たとえば町の名だとか、宿場だとか――をあらわすことばだったのです。
」になった。「人があつまって住んでいるところ」の意です。都、郡、郷、邦などはごくわかりやすいですね。一見したところでは、どうしてこれが「人のあつまっているところ」なのかわからない字――郵とか郎とか邪とか――もありますが、これらも、一つ一つの字についてしらべてみると、もとはみな人があつまっているところ――たとえば町の名だとか、宿場だとか――をあらわすことばだったのです。
だから鄰は、家がかたまっているところ、近隣の家々、ということになるわけですね。
つぎに、左がわの![]() はもとは「阜」の字(岐阜県の阜です)で、これが簡略化されて「
はもとは「阜」の字(岐阜県の阜です)で、これが簡略化されて「![]() 」になった。もともとちがう字が、簡略化によっておなじ形になっちゃったわけです。
」になった。もともとちがう字が、簡略化によっておなじ形になっちゃったわけです。
この「阜」は、「地面が高くなっているところ」の意です。「陸」や「階」はわかりやすい例ですね。「防」などはちょっとわかりにくいが、「堤防」としてみればわかる。川のつつみです。高くなってますね。川のつつみは水のはんらんをふせぐから、それで「ふせぐ」という意味にもちいられるようになった。
そんなふうに、左がわに![]() のつく字は、もとをただせばみな「地面の高み」「土を盛りあげたところ」です。
のつく字は、もとをただせばみな「地面の高み」「土を盛りあげたところ」です。
むかしの中国の町や村は、そのまわりを、土を盛りあげてかこんであった。一つ一つの家もそうであった。もちろん家のまわりのかこみは、町や村のかこみにくらべると低くて簡略ですが、でも一応は土でかこみをつくるのがふつうでありました。まあつまり、日本の家の垣根にあたるものが、中国では土壁であったわけだ。そういう土壁の家がいくつもつらなっている、と解釈して![]() が左にある「隣」の字が書かれたわけだから、この隣のほうだってちゃんと由緒はあるのです。
が左にある「隣」の字が書かれたわけだから、この隣のほうだってちゃんと由緒はあるのです。
「鄰」と「隣」は配置が移動しても同字
鄰と隣とは同じことですが、こんなふうに、字を構成する部分品の配置関係がかわっても同字である、ということはよくあります。
たとえば峰という字。この左がわの山を上にのせて峯としてもおなじことです。どちらが正しくてどちらがまちがいということはない。まったく同資格です。
あるいは音楽鑑賞の鑑という字。この左がわの金を下へ移動して鑒としてもおなじ字です。
あるいは裏と裡。衣と里のくみあわせで、裡はそれが横にならんだもの、裏は里が衣のなかにわりこんだものだが、おなじ字です。
ただし、つねにそうであるとはかぎりませんよ。
たとえば細の字。この左がわの糸を下へ移動すると累。これは累積赤字などの累で、全然別の字になっちゃう。
あるいは忙と忘。リッシンベンは心が形をかえたものだからおなじことなのですが、でも「忙」の左がわを下へもってきて「忘」としたら、別の字になります。まあ忙しいから忘れるんだ、とリクツはつくかもしれませんけど――。
鄰と隣は、移動しても同字、のほうなのでした。
※「有鄰」430号本紙では1ページに掲載されています。
『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。
「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。
ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。
第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。
現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。
- 無断転載を禁じます。
- 無断転用を禁じます。
- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。

