Web版 有鄰 第432号 文士の飲食生活 /山本容朗
第432号に含まれる記事 平成15年11月10日発行
文士の飲食生活 – 特集2
山本容朗
夏目漱石の祝膳
昔、編集者時代、夏目漱石の談話集を編集して、「文士の生活」という一冊を考えたことがあったが、結局、まとまらなかった。その頃から言っても、40年も前のことである。
その時、頁計算までやってあるメモが出てきたので、『清貧の食卓』(実業之日本社刊、のち中公文庫)というアンソロジイの編者あとがきで書いたことを覚えている。
それは漱石が「文士の生活」でしゃべっている食物だけの部分を抜いたものだ。
「私は濃厚な物がいゝ。支邦料理、西洋料理は結構である。日本料理などは食べたいとは思はぬ。尤も此支那料理を或る食通と云ふ人のように、何屋の何で無くてはならぬと云ふ程に、味覺が発達して居ない。幼穉な味覺で、脂つこい物を好くと云ふ丈であ。酒は飲まぬ。日本酒一杯位は美味いと思ふが、二三杯でもう飲めなくなる。
其の代り菓子は食ふ。これとても有れば食ふと云ふ位で、態々買つて食いたいという程では無い。」
漱石に関する食の嗜好は、このご自身の講話と、鏡子夫人の『漱石の思い出』(角川文庫)に出ているが、この文豪が砂糖のついた南京豆のお菓子が好きだったという挿話だけが、強く印象に残る。
漱石の談話は、大正3年(1914)3月22日の『大阪朝日新聞』に掲載されたが、その2年9か月後に漱石は死んでいる。
実は、もう一つ、夏目家の祝膳のことを書いて置きたい。
これは、小宮豊隆の『漱石襍記』(小山書店・昭和10年5月刊)という漱石論集のなかの「日記の中から」という一文から引く。
断わるまでもないが、「日記」は小宮豊隆の明治41年(1908)のものである。この解説のために、小宮自身の注釈を写しておく。
「明治41年は先生42、奥さん32、筆子さん(長女)11、私が25の年であり、先生は前年の4月に朝日新聞に入社し、同じく9月の末に、西片町から早稲田へ越して来た。私は、本郷の森川町に下宿してゐて、この年の7月に大学を卒業することになってゐる。さうして先生の面会日は木曜ときまっていた。」
これで漱石の時代背景はわかる。
さて、3月7日(土曜)の豊隆の日記全文を次に掲げる。
「今日は誕生日だ。雪が積もつて雨が降る。夜先生のところに行く。赤飯、鯛の眼玉のつゆ、鯛の刺身、鯛の味噌焼。」
随分、昔にこの箇所を読んで、夏目家は早稲田の名主の家ゆえ、祝膳に鯛づくしのご馳走が出るのだと思っていた。もう、この時期の鯛はさくら鯛と呼んでいいのだろう。
小宮豊隆日記には、こんな一行もある。
「9月14日(月曜)ゆうべ先生のうちの猫が死んだそうだ。」
食える骨
-
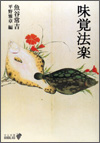
- 『味覚法楽』
中公文庫
埼玉県北部で生まれ育ったせいで、私には鯛を食べる習慣はなかった。鯛の代わりは鮪で、お茶漬け、おつゆなら葱鮪汁、刺身は赤身。近所の魚屋へ大皿を届けておくと夕食時に持ってきてくれた。葱鮪汁には油のあるところ大トロや中トロを使っていたが、こちらはもっぱら切身用である。鯛の刺身を食べたのは昭和14年か15年で、東京・深川の叔父の家である。美味だった記憶だけを忘れて居ない。
それにこの1、2年の間、「いい鯛があったから…」と、うちの老妻が鯛茶漬けを食べさせるようになった。それもお代わりありである。
ここまで書いてくると、魚谷常吉(1894〜1964)という料理人を思い出す。彼には『味覚法樂』(秋豊園出版部・昭和11年7月刊、中公文庫・平成3年)という名高い1冊もある。
『清貧の食卓』を編む時、魚谷常吉の『味覚法樂』から、「干物/食える骨」の2篇を選んで収録させてもらった。
ここで取り上げたいのは「食える骨」の方で、まずは引用する。
「桜で思い出したが、サクラダイの美味は昔から知られているが、その骨の味はあまり問題にされていない。しかし、なかなかうまいもので、中骨を狐色に焼き、擂鉢に入れて擂り潰し、あたたかい飯に振りかけてもよし、あるいはその上から番茶の熱いのをかけても、淡白にして香ばしい茶漬けができる。タイ茶漬けなどの比ではない。」
食味エッセイの面白さ、愉しさは、この鯛なら鯛の同種類の別の作者に表現された文章を読むことであろう。
夏目家の祝膳から「食える骨」とほぼ、同時期に目にした時は、とても嬉しかった。手を叩くほどであった。
幸田露伴のお猪口のお燗
-

- 幸田露伴
漱石の食と鷗外の酒といった小文をものにできればこの上ないのだが、鷗外も漱石同様、酒を嗜まない。それでは、という訳でもないのだが、幸田露伴の酒について少し筆を汚す。
これは文庫版『清貧の食卓』のあとがきに附加した部分にもあるけれど、重複をお許し願いたい。
あれは、いつ頃だったろうか。5年ぐらい前になるのか。日曜日の夜、NHKのあるクイズ番組の担当だという女性から電話がかかってくる。前からクイズの回答を確認する電話を民放からもしばしばもらうことはあった。
「露伴先生は変わった酒豪で、お酒を盃に一杯ずつお燗して飲んでいたというのですが、本当でしょうか」
という問いだった。何か証拠があるんですか、と問い返したが、はっきりした答はなかった。
電話には答えなかったけれど、小林榮子という女弟子と言っていい人が、『露伴清談』(鬼怒書房・昭和22年6月刊)という本を出している。彼女は昭和10年10月頃から露伴のところに出入りしている。
ある日、夕食訪問。その時のことを次のように書く。
「お膳の上には、中々しゃれたお料理が並んでいました。御酒はお猪口に二つずつ年をとった方のお女中が、幾度にもお燗を付けるので、お火鉢に付き切りです。」
この露伴のお猪口2杯ずつお燗の話、それに漱石の祝膳、南京豆に砂糖をまぶしたお菓子の話だって愉しいと思う。誰でも、こんな挿話から作家に親しむようになるのである。
10年ほど前、砂糖をからめた南京豆、浅草のひさご通りの豆屋で買った。「サトビー」と名前で、当時、400グラムで1,400円だった。
雪鍋
-
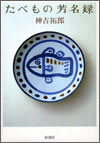
- 『たべもの芳名録』
あまり知られていないが、グルメ文学賞という賞があり、第1回だけで主催者が中止させてしまったことがあった。
準備会に呼ばれたけれど、当時、出版されたばかりの神吉拓郎の『たべもの芳名録』(新潮社・1984年8月刊)を推したことだけを覚えている。が、受賞は新聞記事で知る。
この作品集から、「大根と寒風」という傑作を『清貧の食卓』に選ばせてもらう。
そのお礼にと思ったのであろうか、旅先だと思うけれど、神吉拓郎から、突然、干物が届く。上等で、旨いものであった。そのお礼状に、「大根のミソ汁を、1年のうち360日食べている義兄サンに強い愛着を感じます」と記した。
この義兄サンは、残る日は、豆腐か葱であったと言う。
神吉拓郎は1929年生まれだったから、私より1歳年上だった。同世代といってもいい。この時代、関西には大久保恒次という旨いものを食べる達人がいて、私もその著作をかなり読んだことがある。
神吉拓郎は、大久保恒次の本を愛読し、とりわけ、そのなかに出てくる鍋に20年近くも魅せられている。
要約すると、その鍋は、大久保恒次が、法隆寺の老師から御馳走になる形式になっている。
七輪の上に土鍋がのっていて、そのなかは大根おろし。大根は5本すらないと土鍋いっぱいにならない。
やがて、その大根おろしが音立てて煮えてくる。
老師は、そばの豆腐を杓子ですくい鍋に入れ、おろしにかぶせて、時を見て、「さあ、お上がり」。
神吉拓郎の描写はこんなようだ。
「散り蓮華を使って、小皿に豆腐と大根おろしをすくい取って食べるのだが、これが、雪鍋というものだそうである。豆腐の白、大根おろしの白、そして立ちのぼる湯気の白と、まさに白一色、雪鍋の名にふさわしい料理ではないか。」
今年も、もうすぐ雪鍋の季節になる。
※「有鄰」432号本紙では4ページに掲載されています。
『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。
「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。
ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。
第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。
現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。
- 無断転載を禁じます。
- 無断転用を禁じます。
- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。

