Web版 有鄰 第474号 『略語天国』/藤井青銅 ほか
第474号に含まれる記事 平成19年5月10日発行
有鄰らいぶらりい
『略語天国』 藤井青銅:著/小学館:刊/1,200円+税
いま何かと話題のフリーターは、英語のフリーに、ドイツ語のアルバイターをくっつけ、それを略して日本語にしている、ということをご存知だろうか。カタカナ、ひらがな、漢字、アルファベットに加え、カタカナには外国語も入っている日本語。当然、できあがる略語もいろいろな組み合わせがあり、多岐にわたる。
それに、このごろ漢字はろくに知らない若者が次々と新略語を生み出すから、泥縄とかやぶへびとか鴨ネギなど昔からの略語ぐらいしか知らない年輩者は応対にとまどう。
近年はやったセカチュー、冬ソナ、極妻、古いところでベルばらぐらいは分るが、若者は「あけおめ」だの「ことよろ」だの「メリクリ」などと言ってるらしい。上から順に、明けましておめでとう、今年もよろしく、メリークリスマスのことという。
こうした略語を30種に分類、それぞれのジャンルごとに“略語力”を確かめる問題と解答をつけ、その成り立ちなどの解説をつけている。
もはや普通名詞として、略語の意識もなしに使っている「団地」は「集団住宅地」の略だそうだ。また、独禁法の正式名称は独占禁止法でなく「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」というから役人の言葉もややこしい。
『わが人生の歌がたり』 五木寛之:著/角川書店:刊/1,500円+税
人は世につれ世は歌につれ、というが、この著者のように、幼少にして植民地に渡り、敗戦で九死に一生を得て帰国した波瀾万丈の人生を送ってきた体験者には、その時代時代の歌は、鮮明に脳裡に残っていることだろう。本書は、そんな歌によって紡ぎ出された思い出である。
著者の生まれは昭和7年。「天国に結ぶ恋」や「島の娘」などがはやる一方、「討匪行[とうひこう]」「爆弾三勇士の歌」などがはやり、古賀政男の代表作「影を慕いて」が大ヒットした年だった。ただ、幼少で朝鮮半島に渡った著者が、最初に覚えたのは、「アリラン」の歌だったという。
ソ連軍の略奪と暴行を受けながら、朝鮮を脱出することになるが、戦時下の流行歌も著者の血肉に滞留している。「純情二重奏」や「誰か故郷を想わざる」などで、これらは父に隠れて聴いた曲だ。
敗戦の激動の中で母が死去し、引き揚げてきた父も病気で職を失う。著者は辛うじて高校に通うが、アルバイトの毎日。そんな中で大学進学を父にたのむ。父は家具職人にするつもりだったらしいが、1校だけ受験を許可され、幸いなことに早稲田のロシア文学科に合格。しかしその日から泊まる宿もなくて、神社の床下に寝るありさまだった。
みずみずしい感性を失わないこのエッセーは、「ラジオ深夜便」で放送され、人気の高かったものだが、時間の関係で、一部しか聴かれなかった。今読めるのはうれしい。続編あり。
『日本人のしきたり』 飯倉晴武:編著/青春出版社:刊/667円+税
各地でベストセラーになっているという本だ。一読してみると、たしかに、便利で重宝な本。日本人のしきたり万般、四季折々の行事から冠婚葬祭、手紙や贈答のしきたりに至るまでマナーを教えてくれる。
四季の行事については、正月については省いて、五月五日の「端午の節句」から紹介する。これはもともと女の子の祭りだったという。「端」は「初」を意味し、「午」が「五」と重なることから、五月五日に祭りを催すようになった。発祥は中国だが、日本では田植が始まる前に、早乙女と呼ばれる女の子が、田の神のために仮小屋などにこもり、みそぎをおこなったことに由来する。
この月はショウブ湯やショウブ酒で男も楽しんだが、平安時代になると、勇壮な馬事に転用され、男の催しになったといわれる。
お盆の行事・盆踊りがなぜ賑やかに踊られるようになったのか、酉の市で熊手が売られるのはなぜか、などなど、日本人のしきたりの由来が明かされ、なるほどとうなずかされる。
個人生活の面では、女の人の帯祝いは何の意味があるのか、また生まれた赤ん坊のへその緒はなぜ保存しておくのか、などなど、この1冊で、もの知りになれること請け合い。
『落下する花 月読[つくよみ]』
太田忠司:著/文藝春秋:刊/1,400円+税
-
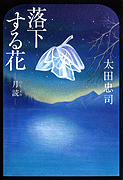
- 『落下する花 月読』
文藝春秋:刊
これはちょっと例のないミステリアスなミステリーだ。冒頭の「落下する花」の書き出しから紹介しよう。
<友喜が初めて月導[つきしるべ]が現れる瞬間に立ち会ったのは、12歳のときだった。その日、彼は星を手の中に掴み取った。>
人が死ぬと何か1つ奇蹟が起こる。友喜が体験したのは祖父が死んだ時で、天井から緑色の草の蔓のようなものが数多く垂れ下がってきた。この月導を読むことを、月読というらしい。月導は日本だけの言い伝えではなく欧州などでも伝えられているという。
全4篇とも、この月読を題材にしたミステリーだが、冒頭の作品についていえば、主人公は友喜で、大学に入り、ある教授の研究室で月読を研究しているという設定。その親しい女子学生に事件が起きる……。
「溶けない氷」の月導はアンドロメダ星雲の形をした天体。空中に漂っていて手の中に収められる。「般若の涙」は、妻を失った義兄の月読の体験。「そこにない手」は、1人ぐらしのアパートで絞殺された中年男の月導。
なお、本来は「月読」とは月齢を数える義だったが、いろいろな神秘的な解釈に敷衍されているらしい。
(K・F)
『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。
「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。
ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。
第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。
現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。
- 無断転載を禁じます。
- 無断転用を禁じます。
- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。
