Web版 有鄰 第477号 『国語辞書 誰も知らない出生の秘密』/石山茂利夫 ほか
有鄰らいぶらりい
『国語辞書 誰も知らない出生の秘密』
石山茂利夫:著/草思社:刊/1,600円+税
日本には辞書批評がないという話を聞いたことがある。『裏読み深読み国語辞書』『国語辞書事件簿』などの旧著でも、こうした辞書信仰に疑義を呈してきた著者が、今回は戦前の花形辞書だった『辞林』『広辞林』、戦後の『広辞苑』などの思わぬ誕生の過程から誕生の秘密に迫っている。
著者は、辞書は「優等生に似ている」という。何でも知っているように見え、事実たいていのことは素早く教えてくれる。
しかし、優等生の優等生たるゆえんは品行方正にみえながらズルをすること。辞書も同様で、正確無比、謹厳実直な顔をしながら「ひと皮むくと名義貸しはあるわ、先行辞書の引き写しはあるわ、間違いのほっかぶりはするわで、ズルの見本市の観」。
辞書に編者として名前の出ている『広辞林』の金沢庄三郎や『広辞苑』の新村出などの著名国語学者は、ほとんど実務にかかわらない名義貸しで、版元の三省堂と金沢、岩波書店と新村家との確執などにふれる。
『広辞苑』は誕生時から新村側の編集のままでは出版できないと判断した岩波側が実質的な編集権を握って全面的な書き直しをした話などが、緻密な取材によって生々しく語られている。著者のいう辞書の謎を解いていく「探偵物語」として興味深く読める。
『歩調取れ、前へ!』 深田祐介:著/小学館:刊/1,600円+税
-
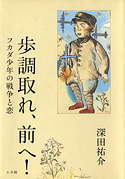
- 『歩調取れ、前へ!』
小学館:刊
副題が「フカダ少年の戦争と恋」とあるように、昭和6年(1932年)生まれの著者初めての自伝小説。敗戦を翌年に控えた昭和19年の正月から話が始まっている。
戦局悪化は決定的となり、食糧難も深刻化したといわれるこの時期、著者一家は妙高の赤倉観光ホテルでちゃんと本格的な洋食を食べ、スキーを楽しんだという。
故・山本夏彦氏は戦前戦中の日本が真っ暗だったというのはためにする嘘、といわゆる暗黒史観を批判していたがそれを裏書するような内容である。
フカダ少年はこの年、旧制の暁星中学に入るのだが、ここで出てくる配属将校(旧制中学以上の学校で教練を教えた陸軍の教官)がユニークである。
大妻女学校の配属将校が鞭で打っていた女学生を助けたり、その後、東部軍管区司令部に移って本土防衛の任務についてからも「皆、アナを掘るのに夢中で他のことが見えなくなっているアナホリス卒業生ばかり」と、アナポリスと呼ばれる米国の海軍兵学校にかけて軍部を批判したりする。
この後、フカダ少年は東京大空襲の悲惨な現場に出かけたり、戦後には父の始めた仕事で倒産したり、辛苦を舐める。
先の大妻の女学生との思わぬ出会いから始まる恋など、まさに波乱の戦時青春で興味深く読ませる。
『銀漢の賦』 葉室 麟:著/文藝春秋:刊/1,381円+税
〈日下部源五が家老松浦将監の異常に気づいたのは八月の昼下がりのことだった。場所は月ヶ瀬藩から領外に抜ける風越峠への道である。月ヶ瀬藩は初代、浅川伊賀守惟茂が徳川家康の側近として蔵入地[くらいりち]代官などを務めていた譜代で、関ケ原の戦で軍功があったとして月ヶ瀬六万五千石の大名に取り立てられた。現藩主、惟忠まで九代を数えている。……〉
この作品は、こうした藩の内紛を丹精な文体で描いていく。
表題の「銀漢」とはなじみのない言葉だが、次のような説明がある。
「知っておるか、天の川のことを銀漢というのを」
それによると、銀は金銀の銀、漢は羅漢の漢だといい、天の川は漢詩では「天漢」「銀漢」などと呼ばれるのだという。
この作品は、源五が家老将監の謎を解いていくという形で展開していく。これまでの時代小説やミステリーとは趣を異にし、静かな語り口で、血の中にひそむ怨念を浮き彫りにしていく手法だ。
今年度松本清張賞受賞作。
『袖のボタン』 丸谷才一:著/朝日新聞社:刊/1,300円+税
男の洋服には2つ3つかならず袖ボタンがついている。あれは何にするのだろうか。それとも何かの名ごりだろうか。
そういえば、かつて男もののズボンには、かならず折り返しがあった。ほこりやごみがたまるだけで、何の役にも立たなかった。それと同じように、袖のボタンも消えていくのだろうか。そんなことを考えながら、全篇一気に読んでしまった。
巧みなユーモアと鋭い批評。コラムとして新聞連載当時から話題になっていたものだ。
「元号そして改元」の項が強烈だ。昭和の後、平成となったが、これは「最悪の名づけ」だという。中国の年号で平の字が上にくるのは一つもないという。日本ではただ一つ「平治」があるだけで、それもごく短期に終わった。
だいたい日本語では、「エ列音」は品格が低く、悪意のこもったマイナス方向の言葉に使われることが多いという。その最たるものが「へ」だと。言われてみれば、もう早急に改元してもらいたいものだ。
日本の詩歌は万葉以来、恋うたを多く採用しているが、中国(漢詩)ではご法度。これはなぜか。日本語は漢詩に由来するものではなくて、南インドのタミル語を起源とするもので、色恋沙汰もその刷り込みによるのだという。
このことを知っただけでも本書を手にする価値がある。
(K・F)
『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。
「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。
ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。
第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。
現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。
- 無断転載を禁じます。
- 無断転用を禁じます。
- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。
