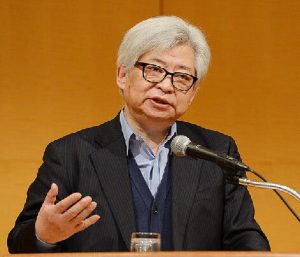Web版 有鄰 第597号 「昭和100年」に想う /保阪正康
第597号に含まれる記事 2025/3/10発行
「昭和100年」に想う
保阪正康
節目の年に
今年(2025)は「昭和100年」、あるいは「戦後80年」でもある。いわば節目の年になるわけだが、それは何を意味するのであろうか。もともと日本社会はこのような節目を大切にする社会で、その時に記念行事を開いたり、特別の思いで節目の意味を考える社会である。
すでに今年もメディアでは、歴史を振り返ったり、あるいはそれぞれの思いを持っての論争なども起こっているようだ。
昭和のなかの近代史と現代史
私の見るところ、「戦後80年」と「昭和100年」は全く意味が異なると思う。初めにこのことを明確にしておかなければならない。よく近現代史という言い方をするのだが、近代史とは明治維新から昭和20年(1945)8月までを指す。この間77年である。現代史とは、日本が太平洋戦争に敗北して新生日本という形での出発を起点に、現在までを指す。戦後80年というのは、実は現代史そのものを指しているといっても良い。戦後80年イコール現代史といった時代区分に重ねるとわかりやすい。
「天皇」「国民」「戦争」の意味の変化
「戦後80年」といえば、現代史を指していて、この期間は近代史の誤り、あるいは錯覚などをどのようにして克服したか、その失敗の教訓を活かしての80年ということになるだろう。もっとわかりやすくいうならば、例えば「天皇」「国民」「戦争」という三つのキーワードを取り出してみれば、すぐにその違いがわかる。次のような違いがあるのだ。
天皇
近代史では現人神(あらひとがみ)
現代史では人間天皇
国民
近代史では臣民
現代史では市民
戦争
近代史では軍事主導主義
現代史では非軍事主導
つまり日本は近代史と現代史では全く様相を異にした国家だったのである。同じ語彙(ごい)でもその意味するところは正反対であったといっても良いであろう。天皇は神として、国民の上に君臨していた近代、それとは真逆に天皇は人間として、国民統合の象徴というのが戦後80年ということになる。
さらに近代史では、国民は天皇の赤子(せきし)(注・子供のこと) とされていたが、現代史では市民とみなされる。いわば基本的人権を持って生まれてきたと解釈されるのだ。選挙権から始まり、表現の自由、職業選択の自由、移動の自由などあらゆる自由が保障されているのである。この基本的自由を自覚することが、現代史の重要な要件である。
「戦後80年」という言葉には、市民社会のルールが込められている。いささか全体主義的な社会から脱した民主主義社会の姿を見ることができ、それが十分に機能しているかを節目の年に確認する必要があるとも言えるであろう。
同時に軍事主導で戦争の時代が続いた近代史の反省として、現代史は非軍事の時代が続いてきた。そのことを自覚し、日本は世界に向かって21世紀の平和論を発信する必要があるとも言えるように思う。この発信がこれからの日本社会に課せられた課題というべきではないかとも、私は考えているのである。
「昭和100年」と「戦後80年」の意味とは
さてそれでは「昭和100年」とはどのような意味を持つのか。すでに書いてきたが、これは「戦後80年」とはどういう違いがあるのだろうか。そのことを考えてみたい。
大正天皇が崩御(ほうぎょ)して昭和に元号が変わったのは、大正15年(1926)12月25日である。つまりこの日は昭和元年の始まりでもあったのだ。昭和元年はわずか一週間しかなかったのだが、この日から昭和64年(1989)1月7日までが昭和という元号の時代であった。その後、昭和天皇の崩御、平成の天皇の生前退位、そして令和の天皇と続いている。従って、「昭和100年」は、昭和天皇が即位してから100年、つまり1世紀が過ぎたという意味になり、そこには平成、令和という二つの元号も含まれていることになる。
20世紀に組み込まれる「昭和100年」
昭和が64年、平成が31年、そして令和が6年余である。この「昭和100年」という語を考える時に、私は二つの視点が必要だと考えている。それは「戦後80年」とは少々意味が違うということでもある。その二つの視点とは何か、それを語ろう。
一、「昭和100年」は「明治100年」とはどのような違いがあるか。
二、「昭和100年」とは20世紀の4分の3、21世紀の4分の1を占めることを考えて見る。
この二つを説明すると、「戦後80年」との違いも明確になってくる。
まず一、から説明するが、「明治100年」の記念式典は昭和43年(1968)であった。当時は高度経済成長の中間期で、日本は国際社会でも「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とその経済発展ぶりが賞賛されていた。太平洋戦争の敗戦から立ち直り、日本社会は自信に満ちていた。まさに司馬遼太郎の『坂の上の雲』の時代だったのである。何より社会的発展が目に見える形で進み、国中が活気に満ちていた。
しかしその後、「大正100年」 という言い方はなかった。つまり元号の持つ意味が活気、隆盛、あるいは国家のアイデンティティ(一体感)が前面に出ている時に、100年という形で私たちはその節目を意識するのである。では「昭和100年」を意識する今年は、どのような背景があるのだろうか。それを確かめるべきであろう(そのことは後述したい)。
そして二、である。「昭和100年」といえば、20世紀の大半と21世紀のわずかの時間が含まれるわけだが、そのことは人類史がこの期間どんな時代だったかを踏まえて、その中で日本はどんな道を歩んだのかが問われなければならない。私の見方になるが、20世紀の中に組み込まれる「昭和100年」は、第一次世界大戦が終わって国際協調の時代で始まり、やがてヒトラーによるナチス政権、イタリアのファシスト政権、それに日本の軍部による軍事独裁政権が生まれて第二次世界大戦が起こる。結局、アメリカを中心とする民主主義国の連合国が勝利して、ファシズム政権は打倒された。この直接の因となったのは原爆の登場である。人類は初めて核兵器を手にしてしまったのだ。
核抑止力下の平和が20世紀の後半から21世紀の今日まで続いている。とはいえ局地的な戦争は続いていて、今でさえロシアによるウクライナ侵略という「戦争」は続いている。
「戦争」と「平和」を問い直す
-
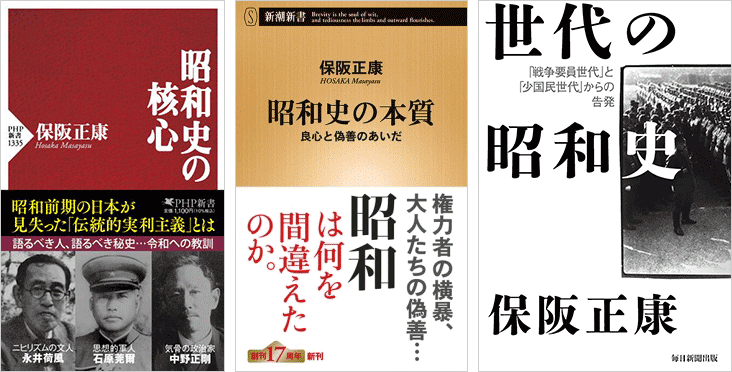
- 保阪氏の昭和関連書より
『昭和史の核心』PHP新書、『昭和史の本質』新潮新書、『世代の昭和史』毎日新聞出版
つまるところ「昭和100年」という時には、人類史も日本社会も「戦争」と「平和」がキーワードになるということである。あるいは「軍事」と「非軍事」がキーワードと言ってもいいかもしれない。私たちが立っている今の時点はこのキーワードをことさらに意識しなければならないのだ。「明治100年」の時もベトナム戦争があったではないか、との反論もあるだろう。しかしロシアのウクライナへの軍事侵略は、ベトナム戦争とは全く違う。
核抑止力下の平和論は、ロシアのプーチン発言(ロシアは存続のかかる戦争では核を使う)によって否定された。さらにウクライナ戦争、イスラエルとハマスの軍事衝突、ここに見えるのはクラウゼヴィッツの「政治の延長に軍事がある」というテーゼが崩壊して、「軍事のあとに政治がある」という逆転現象である。20世紀を支えた理論、概念は崩壊している。「昭和100年」を振り返るときの「戦争」と「平和」は、今新たな形での問い直しがはじまっている、と自覚することが重要だと結論づけて考えてみたい。
私たちは新しい論理や哲学が生まれる時代に立ち会っている。それが節目の今、最も自覚すべきことである。
『書名』や表紙画像は、日本出版販売 (株) の運営する「Honya Club.com」にリンクしております。
「Honya Club 有隣堂」での会員登録等につきましては、当社ではなく日本出版販売 (株) が管理しております。
ご利用の際は、Honya Club.com の利用規約やご利用ガイド(ともに外部リンク・新しいウインドウで表示)を必ずご一読ください。
第410号~573号は税別の商品価格を記載しています。
現在の税込価格は書名のリンク先等からHonyaClubにてご確認ください。
- 無断転載を禁じます。
- 無断転用を禁じます。
- 画像の無断転用を禁じます。 画像の著作権は所蔵者・提供者あるいは撮影者にあります。